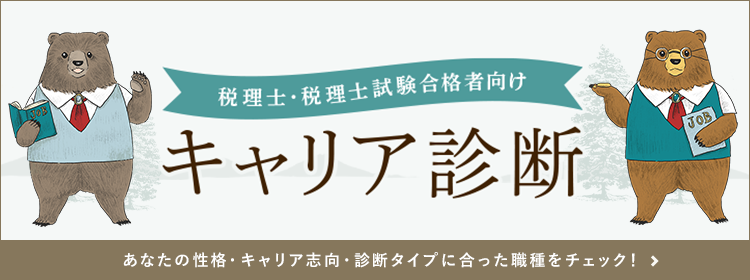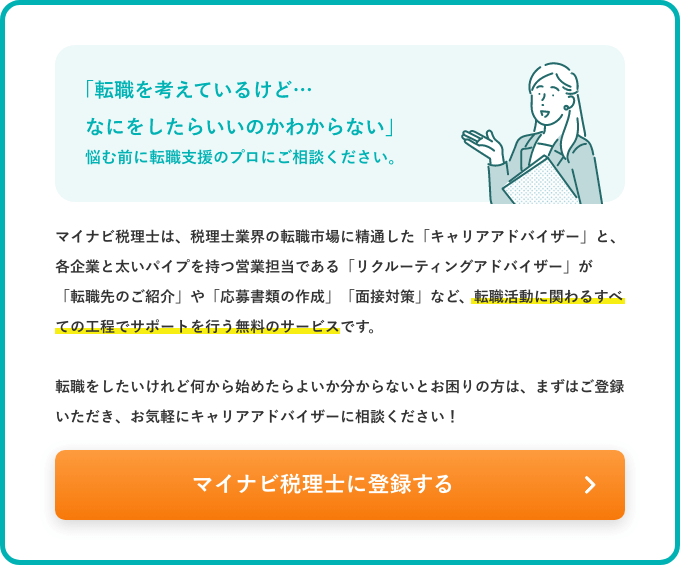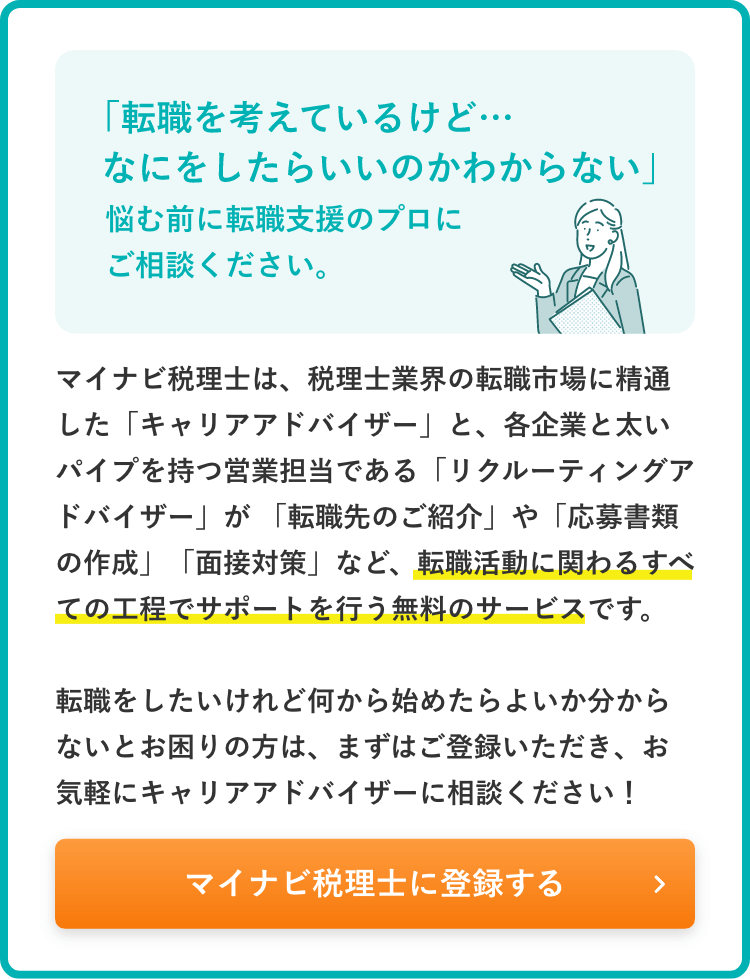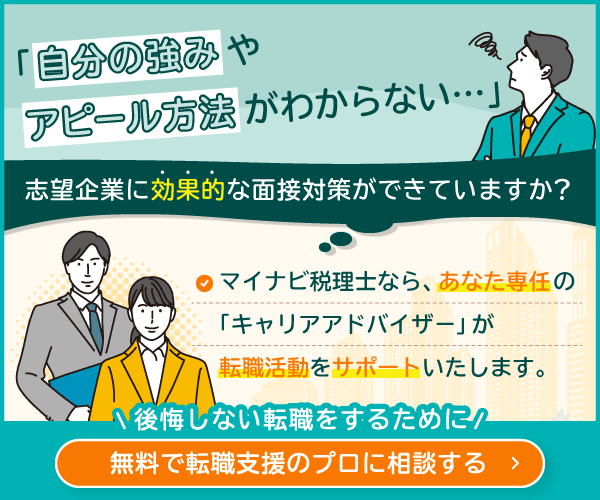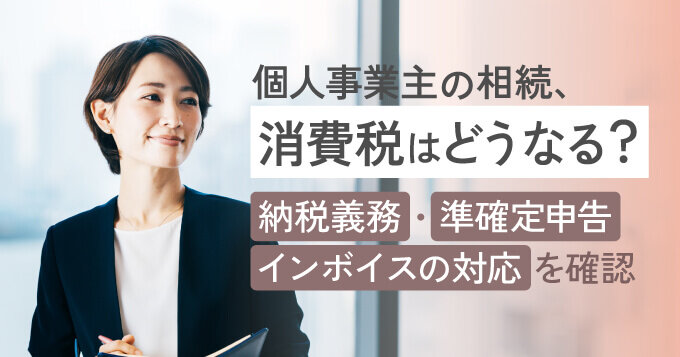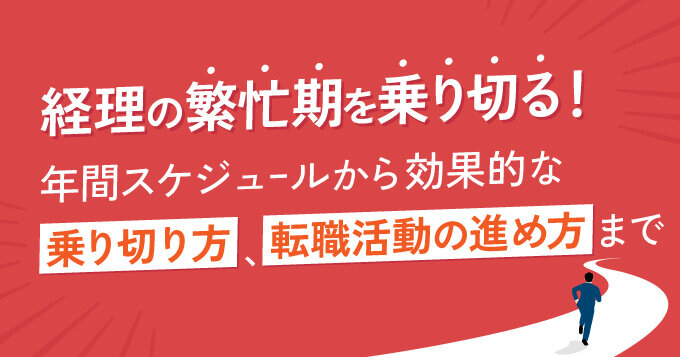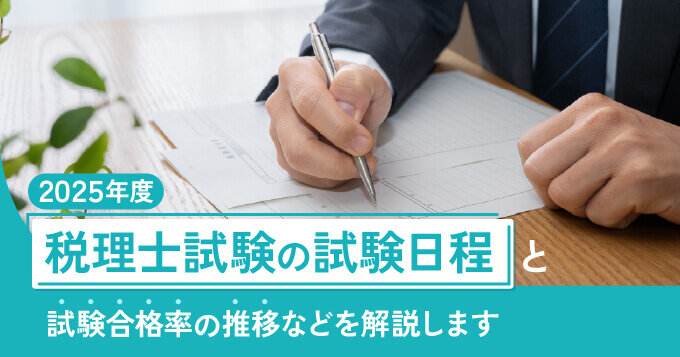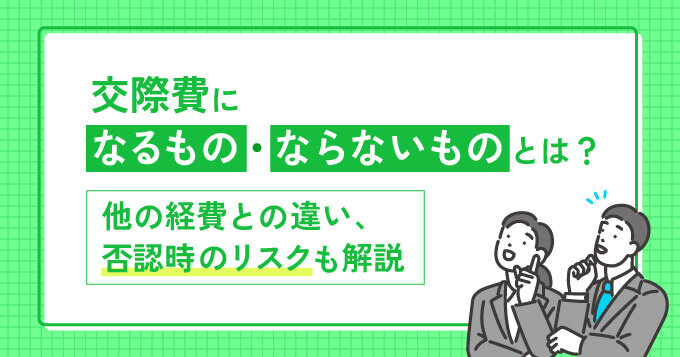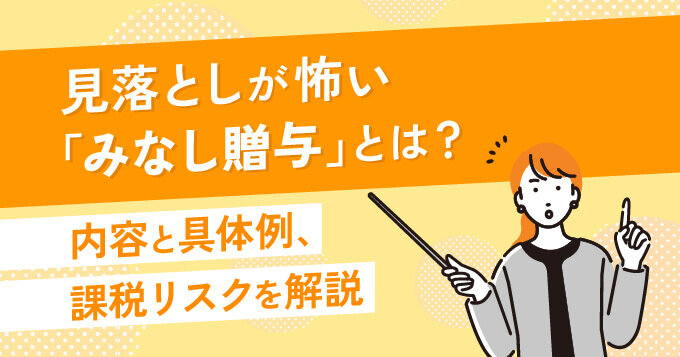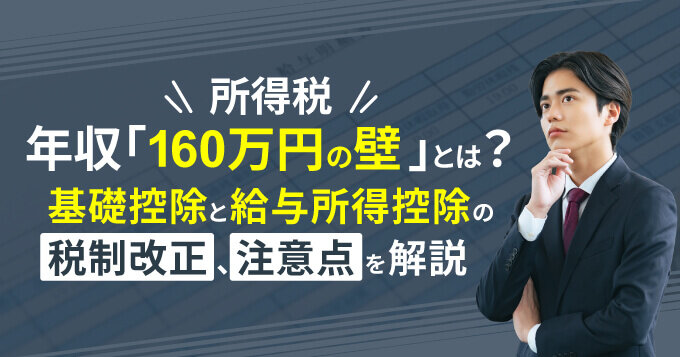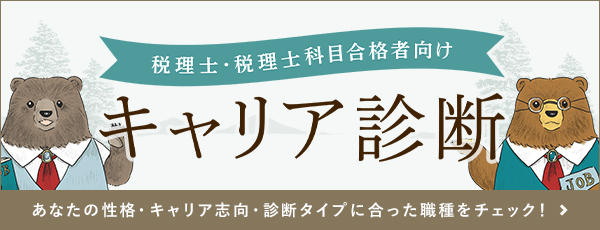税理士補助として働きながら勉強できる?メリットと勉強法・コツを解説
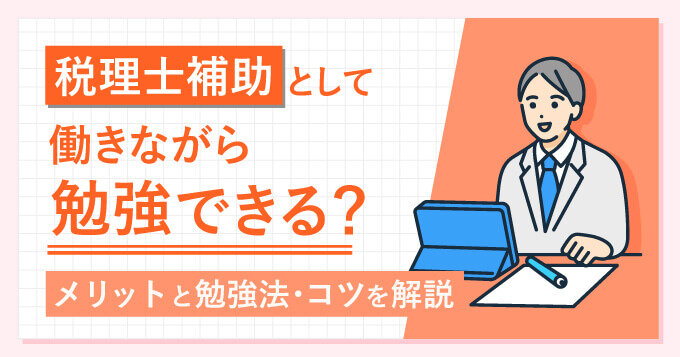
税理士試験に合格した方に話を聞くと、「税理士補助の仕事をしながら勉強をした」という方が意外と多いことに気づきます。実際、税理士の国家資格を取得するには5科目以上の試験に合格する必要があるため、多くの方が仕事と試験勉強を両立させながら、長期戦に臨んでいます。
本記事では、税理士補助として働きながら効率的に試験勉強を進めるためのポイントや、成功のためのノウハウを詳しく解説します。実践的な学習方法や成功のコツも詳しく触れるため、ぜひ最後までご一読ください。

監修
マイナビ税理士編集部
マイナビ税理士は、税理士・税理士科目合格者の方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、税理士・税理士科目合格者の転職に役立つ記情報を発信しています。
目次
税理士補助とは?
税理士補助とは、税理士のサポートをする仕事です。資料作成やデータ入力など、税理士事務所には多様な仕事が存在するので、どこまで携わるかは事務所の方針で決まります。
また、税理士には「独占業務」と言われるものがあります。①税務の代理、②税務書類の作成の代理、③税務相談、この3つは税理士の資格を保有しない人は行うことができません。
とはいえ、すべての実務を税理士が行うことになると、事務所の抱える仕事量に対して人手が足りなくなり、税理士は多忙で倒れてしまうかもしれません。そこで「独占業務以外」を行うスタッフが必要になります。それが「税理士補助」の仕事というわけです。
補助税理士と税理士補助の違い
よく似た言葉なので混同してしまう人もいますが、「補助税理士」と「税理士補助」はまったく違います。税理士資格の有無が最大の違いとなり、それに伴って実施できる業務の範囲も大きく異なります。
補助税理士は税理士資格を持つため、税務代理や税務書類の作成、税務相談などの独占業務を行うことが可能です。ただし、補助税理士制度の下では、自身の税理士事務所を開設できず、また顧客から直接依頼を受けることができないといった制限もあります。
一方、税理士補助は税理士資格を持たない事務職員です。税理士事務所で働きながら、データ入力や書類の整理など、税理士の業務をサポートする事務作業を担当します。税理士法で定められた独占業務を行うことはできません。
税理士試験の勉強をしながら「税理士補助」として働ける?
ネットで「税理士補助」と入力して調べるだけでも多数の求人があり、税理士試験の勉強をしながら「税理士補助」として働いている人はたくさんいます。以下のように、明らかに受験者を念頭に置いているものも少なくありません。
- 税理士をめざしている方歓迎
- 働きながら資格取得も可
- 完全週休2日
- 残業なし
働きながら勉強しようと考えている税理士の卵の方は「税理士補助」を選択肢の1つとして考えてみましょう。両立できるかについて詳しくは、下記ページも参考にしてください。
税理士試験に理解のない事務所もある
「税理士補助」を募集しているからといって、すべての税理士事務所が「試験勉強に理解があるわけではない」ということも頭に入れておいてください。入社してみたところ、試験の勉強がまったくできずにすぐに退職したというケースは少なからず聞きます。
これについては「税理士試験に理解のない事務所が悪い」とはいいきれません。合格をめざす人にとっては「半分勉強、半分仕事」とバイト感覚でも、事務所の経営者や社員にとっては生活がかかっている仕事です。大切なことは、お互いのニーズを事前にすり合わせ、マッチさせることです。
面接の際に「税理士をめざしながら働いている人はいるか」「残業はあるか」「土日出勤はあるか」などの確認をしておきましょう。相手に悪いと思って聞かなければ、相手もあなたのニーズがわからず、入社した後に「そんなことは聞いてなかった」と、Lose-Loseの関係になってしまいます。
税理士補助として働きながら勉強するメリット
税理士補助として、働きながら勉強するメリットは以下の3つです。
- 勉強のモチベーションを保てる
- 実務経験を積める
- 年収を高められる
勉強のモチベーションを保てる
税理士補助として働きながら勉強することは、受験勉強のモチベーション維持に貢献します。実際の税理士の仕事を目の当たりにすることで、目標が具体化され、学習意欲が高まるためです。
例えば、「自分もこうなりたい」というビジョンが明確になったり、職場の先輩が科目合格を重ねていく姿に刺激を受けたりできます。このように、実務の現場で働きながら学ぶことは、長期にわたる受験勉強を継続するための強い動機付けとなります。
実務経験を積める
税理士試験対策と実務経験を同時に積めることも、大きなアドバンテージとなります。税理士補助として働いた経験は、将来的に税理士登録に必要な2年の実務経験として扱われるからです。
また、日々の仕訳業務、決算書作成、税務申告書の作成補助など、実践的な経験を通じて、テキストだけでは得られない生きた知識も蓄積できます。顧客とのやり取りを通じて、コミュニケーション能力も自然と身につくでしょう。
年収を高められる
税理士補助として働きながら資格取得を目指すことは、着実な収入アップを目指す手段にもなります。科目の合格数に応じて、段階的に資格手当で給与を上げる仕組みを整えている税理士事務所もあるからです。
1科目の合格での資格手当は、おおよそ5,000円〜1万円ほどが一般的です。5科目の合格者であれば550万円以上を目指すこともできます。最終的には、税理士の資格を手にしてさらなる年収増も狙えます。
税理士補助として働きながら勉強するデメリット
税理士補助として働きながら勉強するデメリットは、以下の2つです。
- 勉強時間が少なくなる
- 家計に影響を与える
勉強時間が少なくなる
税理士補助として働きながら勉強することは、純粋な受験勉強時間の確保が難しくなります。フルタイムでの勤務であれば平日は1日あたり8時間前後、確定申告時期などの繁忙期には残業も増えます。
税理士試験の勉強に理解がある事務所でも「仕事は仕事」なので、疲れて帰宅してから勉強できるかどうかはその人次第です。「仕事が大変なので勉強する時間がとれない」となってしまえば、合格までの期間が長期化する可能性が高くなります。
「税理士は何事も経験が大切」「勉強だけでは身に付かないものがある」「将来をイメージできる」などのメリットはあるものの、時間・体力の配分には留意しましょう。
家計に影響を与える
税理士補助として働く、特に未経験からの転職の場合、収入面の課題を抱えることもあります。家を出て自分で稼ぎながら勉強する際、生活費に加えて、講座受講料、教材費、模試受験料などの支出が必要となります。
初任給は未経験からの転職の場合、月収は20~25万円程度(年収300~400万円)からのスタートが一般的です。もちろん、科目合格や任せられる仕事内容によって徐々に上昇しますが、一時的にでも収入減と学習費用の二重の経済的負担が発生します。特に家族がいる場合は、慎重な資金計画を立てましょう。
勉強と両立のしやすい環境は、就職・転職する税理士事務所によって大きく異なります。悩んでいる方は、マイナビ税理士へ、ご自身の状況や希望条件についてご相談ください。受験生の方に理解のある事務所や、年収条件にマッチした求人など、あなたに最適な環境をご提案いたします。
税理士補助と並行した試験勉強にかかる期間
税理士試験に挑戦しながら税理士補助として働く場合、合格までの道のりは一般的に5年程度を見込む必要があります。実務経験を積みながら年間1科目の合格を目指すペースを想定しています。
特に実務未経験からスタートする場合は、基本的な業務に慣れるまでの期間として1年程度の余裕を持たせ、6年計画とするとよいでしょう。ゆとりある計画設定により、実務と試験勉強の両立が無理なく進められ、着実な合格への道筋を立てることができます。
税理士補助と並行した試験勉強は『自学力』がポイント
税理士事務所で働きながら試験勉強をする場合、実務や実際の試験について先輩や上司が付きっきりで指導してくれる環境はまれです。単なる放置ではなく、税理士業界に根付いた「自ら調べ、学ぶ」という文化があるためです。
税法は毎年のように改正が行われ、自身が常に最新の知識をアップデートしていく必要があるため、自学力は税理士として不可欠な能力となります。一見厳しく感じるかもしれませんが、先輩たちも同じ道を歩んできており、自学の姿勢は将来税理士として活躍する上で大きな財産となるのです。
税理士事務所の仕事に慣れるまでは基礎固めから
税理士試験の勉強を始める前には、税理士事務所での実務に慣れることが大切です。実務は、知識をつけなければ対応できず、自然に知ろうとすることで試験勉強にも直結します。まず、仕事を覚えるためにも、以下に挙げた4つの基礎固めに集中しましょう。
- 日常的に使用される会計・税務の専門用語を理解する
- 記帳代行や確定申告など1日の業務の流れを覚える
- 実務で使用する会計ソフトの基本機能を習得する
- 日々の取引・仕訳に必要な勘定科目を覚える
焦って試験勉強を優先すると、かえって仕事に支障をきたし、両方が中途半端になってしまう可能性があります。仕事によく使う基礎を固めることで、自然に試験科目の理解も深まり、効率的な学習につながるのです。
税理士補助として働きながら勉強する方法
税理士補助として働きながら勉強する代表的な方法には、以下の5つが挙げられます。
- ハウツー本や税法に関する解説本を使う
- 通信・専門学校へ通う
- 事務所にある過去の記録から学ぶ
- 実務から知識を蓄積する
- セミナーに参加する
ハウツー本や税法に関する解説本を使う
税理士の実務や税法を学ぶ際は、まずは分かりやすく書かれた入門書からはじめることを基本とします。特に税法は専門的で難解な内容を含むため、いきなり専門書に取り組むと挫折してしまいかねないからです。
所得税法や青色申告の超入門シリーズ、実務で頻繁に使用する法人税実務の基礎など、実務に即した解説がされている書籍を選ぶと良いでしょう。実務未経験者の場合、基本的な業務内容や役割を理解できる入門書であれば、仕事の全体像の把握にも役立ちます。
通信・専門学校へ通う
専門学校や通信教育は、働きながら税理士試験の勉強を進めるうえで効率化を目指したい方の選択肢です。体系的にまとめられていることから、迷うことなく学習を継続しやすいです。
例えば、大手の専門学校では、年間1科目合格を目標とするなど、実務と両立しやすいカリキュラムが用意されています。通信教育では、自らのペースで学習を進められる利点もあり、繁忙期と試験勉強のバランスを取りやすいという特徴があります。
事務所にある過去の記録から学ぶ
税理士事務所に保管されている過去の記録は、実際の事例から学べる生きた学習教材として価値があります。同じような業種・規模の企業における過去の記録を参照しつつ、実務での対応方法を学べるでしょう。
外部へ持ち出すことのできないものばかりではあるものの、具体的な取引や申告事例が含まれており、教科書では学べない現場の知恵が詰まっている教材を逃す手はありません。個人情報や機密情報が含まれるため、必ず上司の許可を得たうえで、適切な範囲内での活用を心がけてください。
実務から知識を蓄積する
税理士補助として働く際、実務を通じた知識の蓄積も試験勉強の方法として挙げられます。以下のような媒体から、実務に使う知識と同時に、試験に関連する情報も集めておきましょう。
- 日弁連HP
- 国税庁
- MyKomon TAX
- 税務通信
また、実務で出会う新しい勘定科目については、[経済]簿記勘定科目一覧表などを活用して、その場で調べる習慣をつけることも大切です。このような日々の積み重ねが知識の蓄積につながり、税理士試験の学習にも活きてきます。
セミナーに参加する
事務所経由で案内されるセミナーは、税理士補助で働きながら最前線で活躍する専門家から直接学べる機会です。法改正の実務的な影響や対応方法、実際の事例に基づく解説など、教科書だけでは得られない知識を学ぶことができます。
また、他の参加者との交流を通じて、さまざまな視点や考え方に触れることで、自身の知識の幅を広げることもできます。将来税理士として独立した際にも財産となりますし、疑問点があれば講師に直接質問できることで理解も深めやすいでしょう。
税理士補助として働きながら勉強する際のコツ
税理士補助として働きながら勉強する際のコツには、以下の5つが挙げられます。
- わからないことはすぐ調べる
- 自分の意見を持ってから周りに聞く
- スキマ時間を活用する
- 何をやるのかを明確にする
- 勉強は毎日続ける
わからないことはすぐ調べる
税理士補助として働きながら勉強する場合は、『自学力』を磨くのが基本です。税法は毎年のように改正され、顧客企業ごとに適用される法規も異なります。わからないことがあった時、まずは国税庁のホームページや税務通信などの信頼できる情報源で調べる習慣をつけましょう。
実際の業務では教科書通りにいかないケースも多いため、過去の記録から参照するのも有効な方法です。「調べる習慣」は単なる知識の獲得だけでなく、問題解決の糸口を素早く見つける力の養成にもつながる立派な勉強です。
自分の意見を持ってから周りに聞く
税理士事務所で働く際には、「これはどうすればいいですか?」といった漠然とした質問は避ける癖をつけておくことも大切です。補助として働いているとはいえ、「そんなこともわからないの?」と言われかねません。
まず自分で考え、「この条文についてこのように解釈したのですが、この理解で正しいでしょうか?」というように、自分の考えを示したうえでの質問を基本にしましょう。
- 先輩や上司が質問者の理解度を把握しやすく的確なアドバイスができる
- 自分で考えることで理解が深まり同様のケースを自力で解決できる力がつく.
上記に挙げた2つのメリットがあるほか、将来にはアドバイザリーを担う際にも役立ちます。
スキマ時間を活用する
税理士事務所で働きながら試験勉強を続ける際は、繁忙期でも続けられるスキマ時間の活用も考えましょう。忙しくて時間がないという方でも、1日の時間割を細かく書いてみると意外に使える時間があることに気づけるはずです。
例えば、SNS等を見ている時間があるなら勉強に充てるというだけでも、一定の勉強量を確保できます。実際に書き出してみないとわからないことも多いため、見つけたスキマ時間に電子書籍で最新の税法改正について学んだり、MyKomon TAXで最新情報をチェックしたりするなどに取り組んでください。
何をやるのかを明確にする
税理士補助として最初に任される業務は、主に記帳代行、法人の決算申告、個人の確定申告、税金相談、年末調整の5つです。業務に必要な知識を選択し、何をやるのかを明確にするだけで勉強の効率を高められます。
大切なのは「できればいいな」で決めるのではなく、「やるべきこと」だけに絞ることです。ゴールがなければ勉強の意欲も保てません。年単位で試験勉強を続けることを考えて、できるだけゴールのハードルを下げて、本を1ページ読むといった具合に簡単なレベルから積み上げてください。
勉強は毎日続ける
最後に、日々の勉強を継続させるコツとして、1ページ、1単語、1テーマなど、何をゴールにしても良いので毎日続けることが重要です。特に働きながらの勉強では、自分のペースを守り、長期的な視点で自分に合った学習リズムを見つけましょう。
たとえ15分でも、毎日の「今日はこれをやった」という積み重ねが、確実な知識の定着につながります。そして、小さな進歩を認め、自分を褒めて自己肯定感を高める習慣が身につくと、モチベーションも高くなり勉強量は自然と増えていきます。
税理士補助として働きながら独学で試験合格は可能?
税理士補助として働きながらの独学での試験合格は、困難ですが不可能ではありません。むしろ、税理士補助として働くことには以下のような優位性があります。
- 実務経験を通じて試験知識の理解が深まり、記憶の定着がしやすい
- 税理士の仕事を間近で見ることでモチベーション維持がしやすい
- 先輩からアドバイスや試験のノウハウを得られる
- 資格取得支援制度がある事務所も多い
合格には平日2時間、土日6時間程度の継続的な学習時間の確保が必要です。5科目合格に必要な総学習時間は1800〜1950時間と言われており、働きながらでは相当な時間を要します。
詳しい勉強方法や科目選択のポイント、おすすめの教材など、独学で税理士試験に合格するためのより詳細な情報は、下記ページもご覧ください。働きながら税理士資格取得を目指す方に向けて、具体的な戦略とアドバイスを詳しく解説しています。
まとめ
税理士補助として働きながらの試験勉強は、実務経験と専門知識の習得を同時に進められる方法です。仕事に慣れるまでの期間を設け、基礎固めを重視しながら、自学力を養うことが重要です。
スキマ時間の活用や日々の継続的な学習習慣を確立し、実務と試験勉強の相乗効果を最大限に活かすことで、着実な合格への道を歩むことができます。
税理士試験の勉強と両立できる環境選びから、合格への道ははじまっています。理解のある税理士事務所で働きながら、効率的に実務経験を積みたい方は、ぜひマイナビ税理士にご相談ください。あなたの希望条件や状況に合わせて、最適な税理士事務所をご紹介いたします。
マイナビ税理士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
マイナビ税理士とは?
マイナビ税理士は税理士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
あわせて読みたいオススメ記事
カテゴリから記事を探す
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。