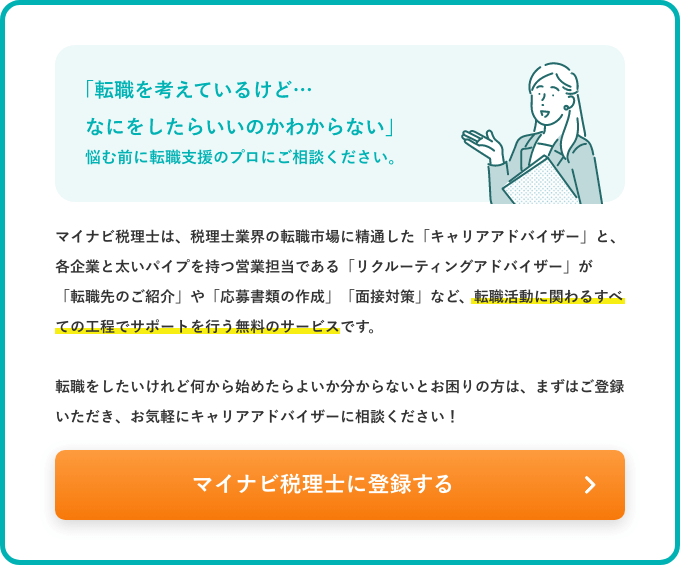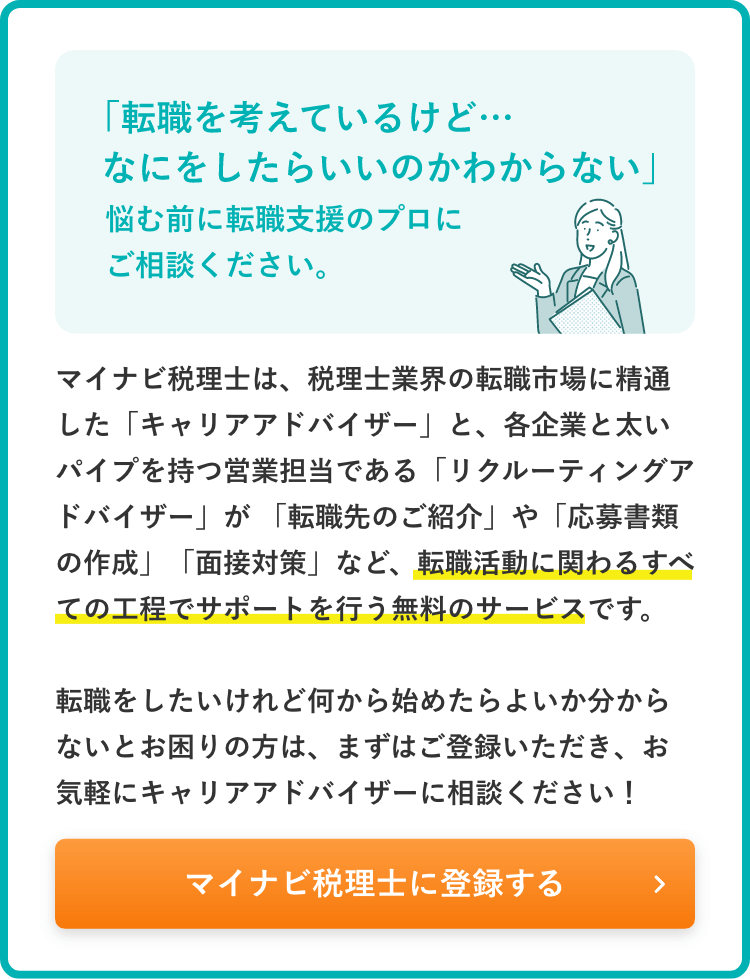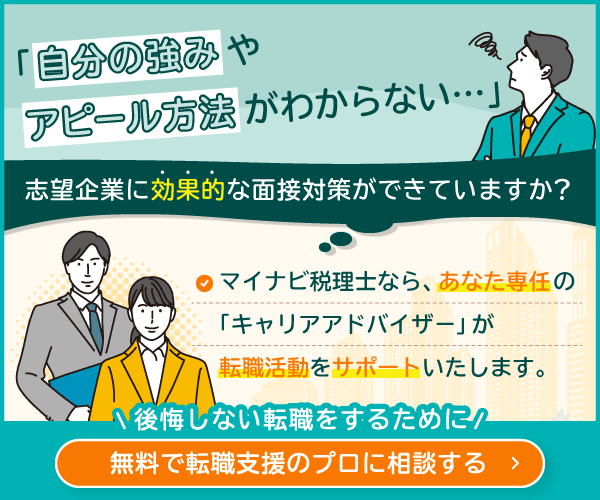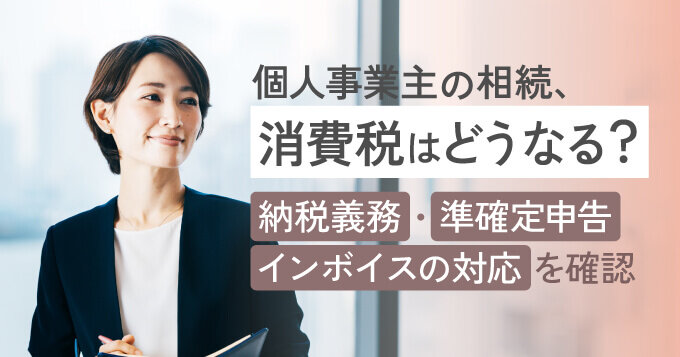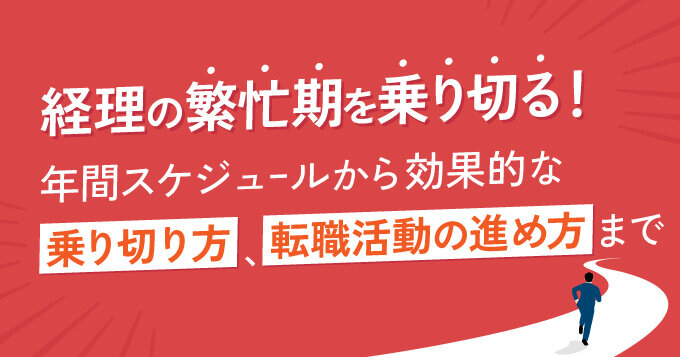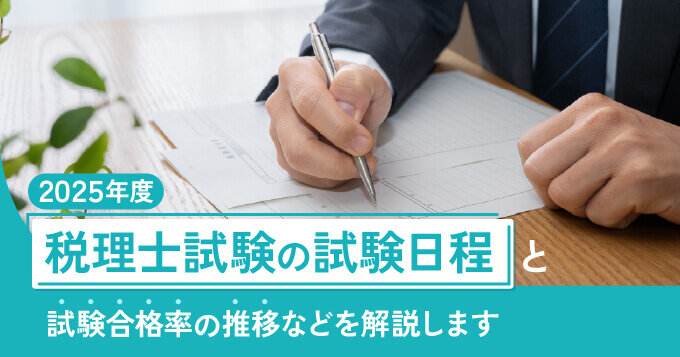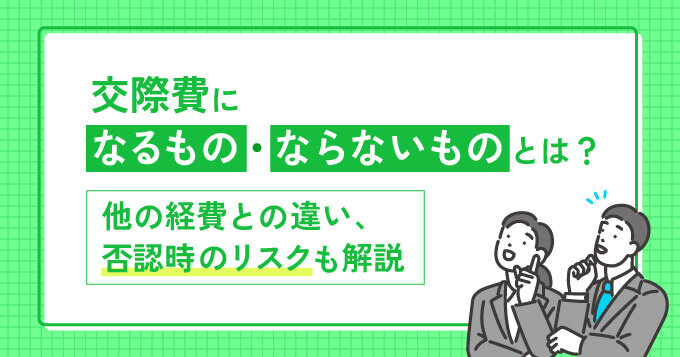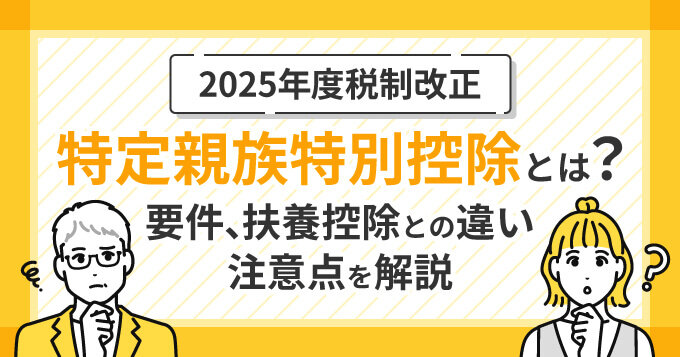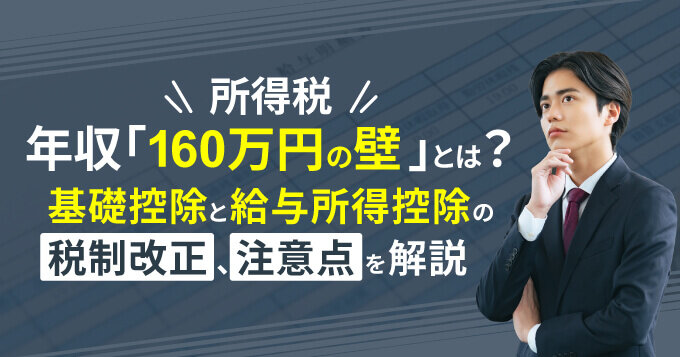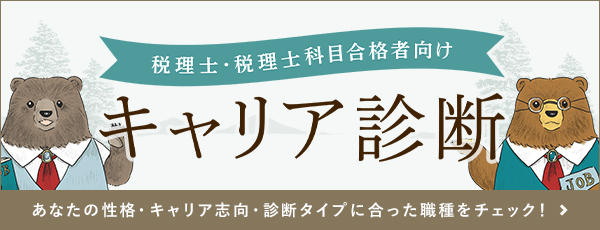見落としが怖い「みなし贈与」とは?内容と具体例、課税リスクを解説
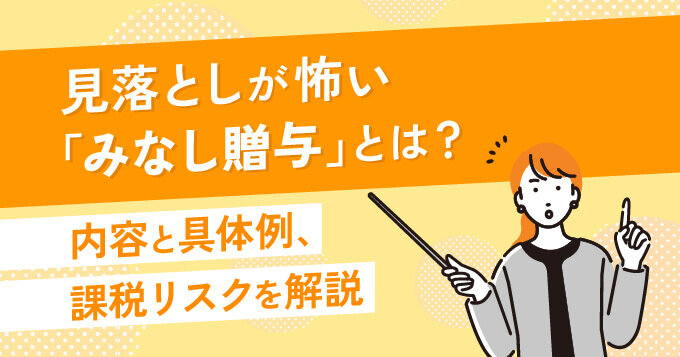
みなし贈与とは、税法独自の考え方です。民法上の贈与の要件を満たしていなくても、実質的に贈与としての経済効果があるとされる場合に贈与とみなして課税されます。きちんと把握していないと、思わぬ課税リスクが生じることにつながりかねません。特に相続時精算課税制度の適用がある場合には注意が必要です。今回はみなし贈与の内容と具体的な例、そして課税リスクについて解説します。
目次
みなし贈与とは何か
みなし贈与とは、民法上の贈与が成立していなくても、相続税法で贈与としてみなされる経済的な利益の供与を言います。相続税法では、民法上の贈与だけでなく、税法上で「これは贈与である」とみなしたものも贈与税の対象としています。
民法上の贈与との違い
一般に、贈与は民法上の贈与を言い、次のようになっています。
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
ポイントは次の3つです。
- 「あげます」「もらいます」と贈与者・受贈者ともに合意していること(諾成契約)
- 受贈者は無償で財産をもらうこと(無償契約)
- 贈与者のみが財産を渡す義務を担う。受贈者には財産を受け取る権利だけがある(片務契約)
この3要件を満たせば民法上の贈与が成立します。そして受贈額が年110万円を超えれば、暦年贈与課税制度・相続時精算課税制度のいずれかで贈与税が課されます。
しかし世の中には「民法上の贈与は成立していないけれど、実質的に一方の財産が増え、経済的利益を享受している」という経済行為もあります。たとえば「借金の肩代わり」「生命保険料の受取人と保険料の負担者が異なる」などです。こういった「民法上の贈与は成立していないけれど、実質的に贈与と同じ経済効果が生じている」ものについて、贈与と同等に扱われます。
規定の趣旨
みなし贈与の規定の趣旨は「贈与税の負担を不当に回避する行為を防止するため」です。もし、実質的に贈与と同様の経済効果があるにもかかわらず、形式的に贈与契約を結ばないことで贈与税を免れることができるとすれば、課税の公平性が損なわれてしまいます。そこで税法でみなし贈与の規定を設けることで、不当な税逃れを防止しているのです。
みなし贈与の具体例
みなし贈与にあたる行為として、主に次のようなものがあります。
不動産や株をかなり低い金額で親族に譲渡した
個人間で不動産や非上場株式、美術品などを時価よりも著しく低い金額で譲渡すると原則、みなし贈与となります。たとえば、時価5000万円の不動産を子に100万円で譲渡したケースです。この場合、4900万円がみなし贈与となり、贈与税の対象となります。要は「本来5000万円払うべきところ、たった100万円で買えた。つまり、残りの4900万円は実質贈与を受けたようなものだ」と考えるわけです。
気になるのが「譲渡対価がいくらだとみなし贈与になるのか」です。これは個別に検討していくしかありません。また、ここでいう時価は土地や借地権、家屋や構築物だと、その時点の市場での取引価格となりますが、それ以外については相続税評価額を指します。
ただし、著しく低い金額で譲渡したケースであっても、次の要件すべてに当てはまる場合は例外です。譲渡されても債務弁済が困難な部分については、みなし贈与とはなりません。
- 譲渡される側(購入する側)が資力を喪失して債務弁済が困難であること
- 譲渡そのものが譲渡される側の扶養義務者から行われたこと
- 譲渡された資産が債務弁済に充てるためのものであること
身内の借金を肩代わりした
親族の抱える借金を無償で肩代わりすると、その債務免除益は原則、贈与とみなされます。たとえば、子が親の1,000万円の借金を代わりに返済した場合、親はその1,000万円相当の経済的利益を得たとして贈与税が課されるのです。肩代わりだけでなく、直接貸し手から借金を帳消しされたケースもみなし贈与として扱われます。
ただし、債務者が資力喪失して債務弁済が難しくなっているケースは別です。債務の全額あるいは一部を債権者から直接免除されたり、扶養義務者が肩代わりをしたりしても、みなし贈与とはなりません。
生命保険の受取人は自分だが保険料は親が負担
生命保険契約において、保険金の受取人が子であるにもかかわらず、保険料を親が負担しているのなら、受取保険金は子が親から贈与されたものとみなされます。保険金を形成するのに必要な保険料を自分自身ではなく親が負担しているためです。
子の納税義務を肩代わりした
子が負担すべき税金を親が無償で肩代わりした場合は、税額相当額が子への贈与とみなされることがあります。親の肩代わりによって子は納税債務がなくなり、経済的な利益を得るからです。
ただし、親の肩代わりが一時的な立替に過ぎないのなら、みなし贈与となりません。
同族会社に個人の財産を贈与した
個人が同族会社に財産を贈与した場合、同族会社の株主にみなし贈与による贈与税の課税の可能性が生じます。同族会社に財産が贈与されるということは、贈与された分だけ会社の株式評価が上がるからです。結果、贈与した個人から株主に対し、株式の価値の増加分だけ贈与があったとみなされて課税されるおそれがあります。
余談ですが、この場合、贈与者についてはみなし譲渡課税、同族会社には法人税の受贈益課税にも注意しなくてはなりません。
みなし贈与の課税リスク
みなし贈与と判断されると、通常の贈与と同様に贈与税が課されます。期限後に発覚したのならば、無申告加算税または過少申告加算税、延滞税がかかります。
贈与税の申告が必要なことも
みなし贈与に該当すると原則、贈与税の申告が必要です。ただし、贈与税には暦年課税制度・相続時精算課税制度のいずれにも基礎控除があります。そのため、1年でもらった財産の金額が110万円までなら贈与税はかかりません。つまり、みなし贈与で受けた経済的利益があっても、ほかの受贈額と合計して年110万円以下なら贈与税の申告も納税も不要です。
しかし、みなし贈与の金額がこの基礎控除額を超える場合は、申告と納税が必要になります。申告期限は、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までです。期限内に申告・納税を行わなかった場合、加算税や延滞税が原則かかります。
相続時精算課税制度の対象に
相続時精算課税制度は、基本的に、生前に贈与された財産も相続財産に足し戻して相続税額を計算する制度です。相続時精算課税選択届出書の対象となった贈与からずっと適用されます。二度と暦年課税制度には戻れません。そのため、次のようなリスクが生じます。
みなし贈与も相続財産に持ち戻し
相続時精算課税制度の対象となる財産は民法上の贈与だけではありません。税法独自のみなし贈与も対象です。つまり、贈与者の生前、受贈者に対するみなし贈与があるなら相続財産に加算しないといけないのです。みなし贈与を含めた受贈額が年110万円以下なら相続財産への加算は不要ですが、そうでないなら「1年間の受贈額(贈与時の時価)-110万円」を相続財産に持ち戻す必要があります。
贈与税の申告が必要
また、みなし贈与額を含めた生前の受贈額が年110万円を超えるなら、贈与税の申告を期限内に行わなければなりません。たとえ累計2500万円という特別控除額の枠内であったとしても、です。期限後になれば一律20%の税率で贈与税がかかります。
相続人でない孫でも相続税の申告が必要に
相続時精算課税制度は「贈与者が60歳以上の父母または祖父母」「受贈者が18歳以上の子または孫」が前提です。もし、相続人でない孫がみなし贈与を受けた場合、相続発生時にはその孫も相続税の申告・納税義務を負う可能性が生じます。
おわりに
みなし贈与は、税法独自の考え方であるため、なかなか気づきにくいところがあります。特に注意したいのは相続時精算課税制度の適用を受けているケースです。贈与者の死亡後、申告漏れが生じるおそれがあります。顧問先との会話で、みなし贈与に該当するものがないかには気を配っておいた方が無難かもしれません。
マイナビ税理士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
マイナビ税理士とは?
マイナビ税理士は税理士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。