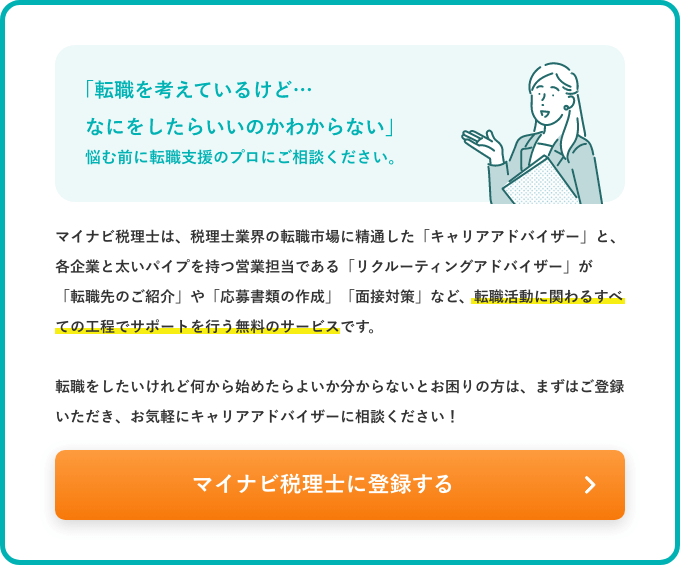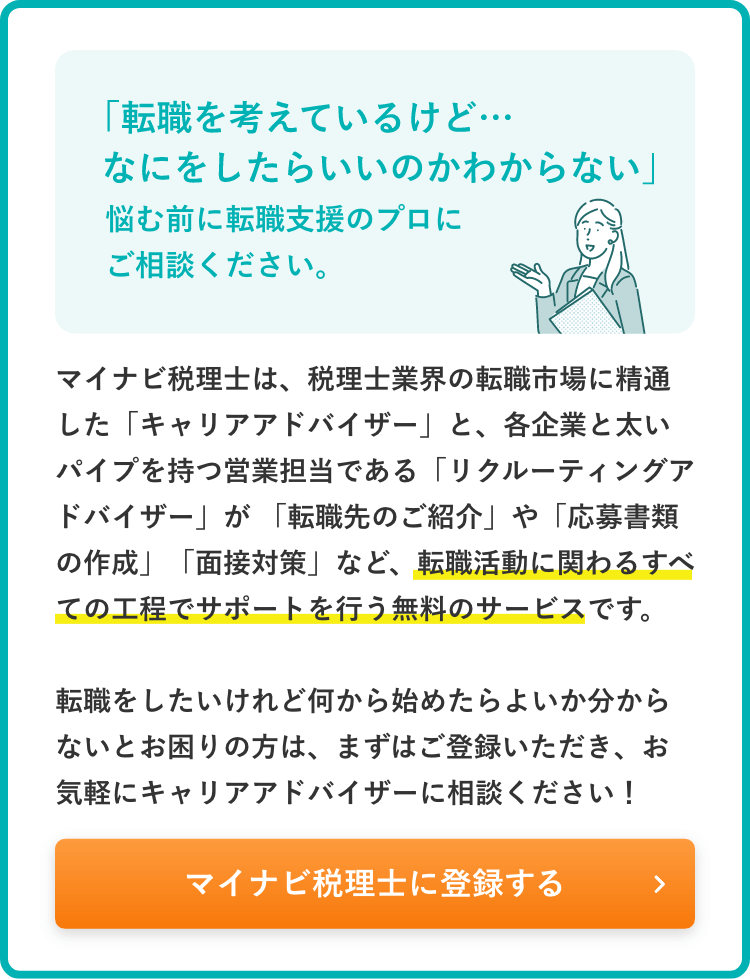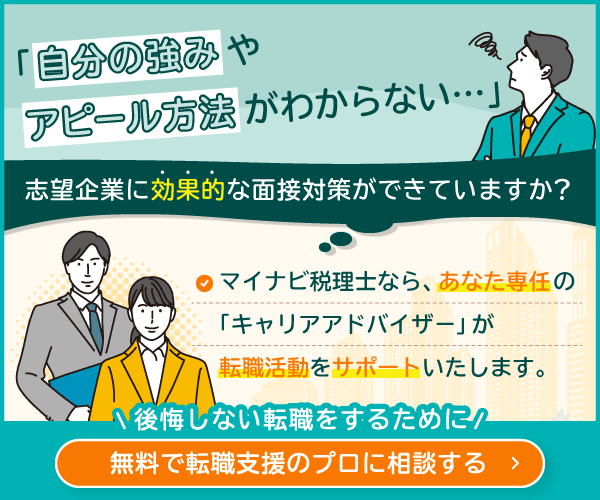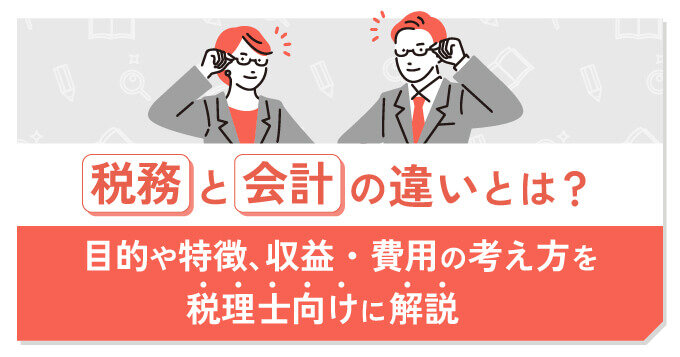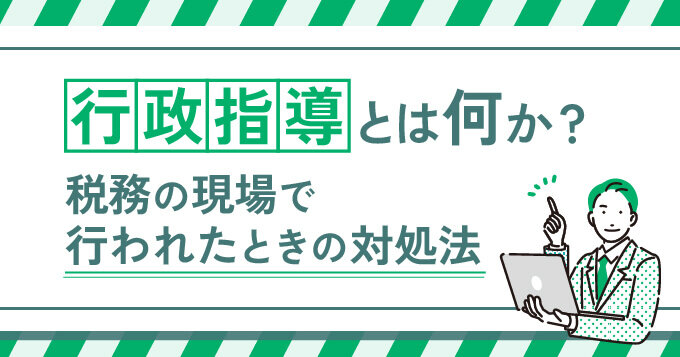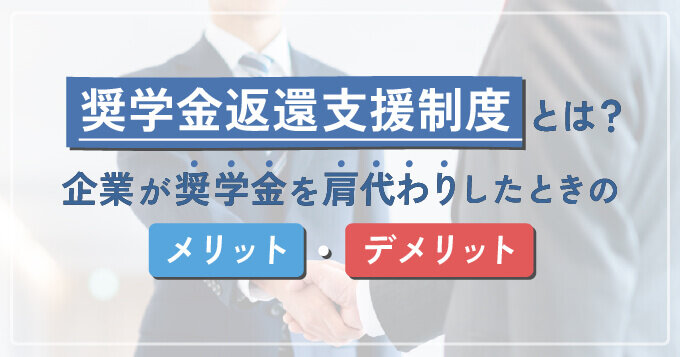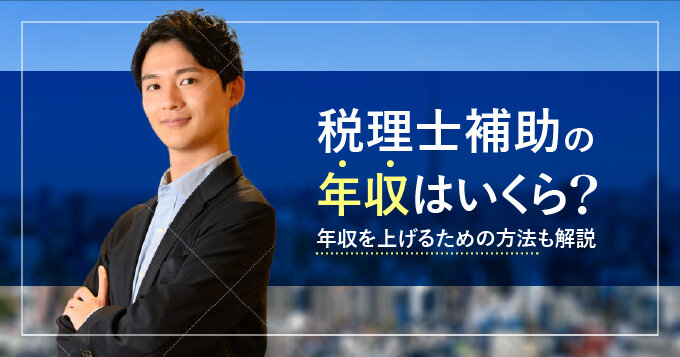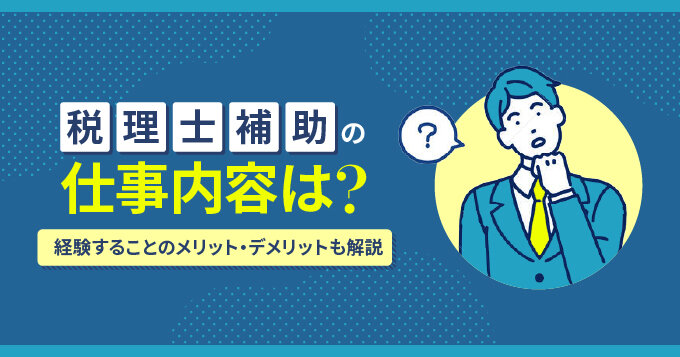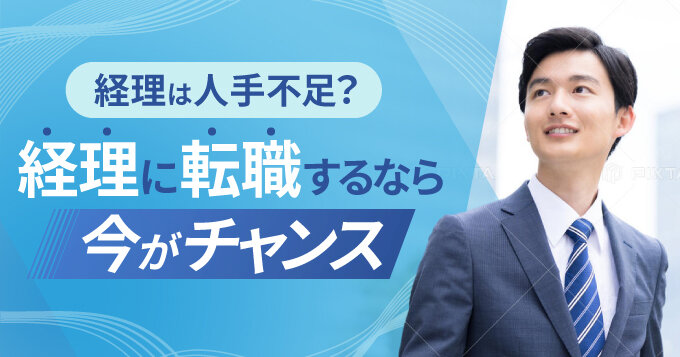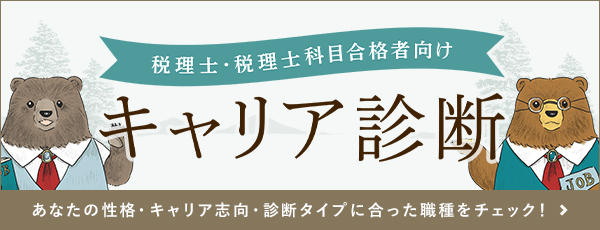税理士試験の受験資格は?受験資格をなるべく早く満たす方法

税理士になるためには、会計学から2科目・税法から3科目、合計5科目に合格する必要があります。会計学に属する科目は、簿記論と財務諸表論の2科目で固定です。
一方、税法に属する科目は所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、国税徴収法などから3科目を選択します。ただし、所得税法か法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。
令和5年度(2023年)から税理士試験の受験資格が緩和され、会計学科目の受験資格は撤廃となりました。しかし、税法科目については依然として受験資格があり、学識、資格、職歴のいずれかの要件に該当していないと受験できません。
この記事では、税理士試験の受験資格について詳しく解説し、受験資格がない場合の対策方法も紹介します。
関連まとめ記事
税理士試験情報まとめ 受験資格・申し込み手順
効率よく税理士の資格取得を目指している方や、働きながら税理士試験の合格を検討している方は、マイナビ税理士のキャリアアドバイザーへお気軽にご相談ください。実務経験を積みながら税理士資格を取得するためのキャリアをサポートいたします。

監修
マイナビ税理士編集部
マイナビ税理士は、税理士・税理士科目合格者の方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、税理士・税理士科目合格者の転職に役立つ記情報を発信しています。
目次
税理士試験の受験資格は?
税理士試験の受験資格は、現在は税法科目にのみ設けられています。受験資格は「学識」「資格」「職歴」「認定」の4種類に分類され、いずれか1つの要件を満たせば、税法科目の受験資格が認められます。
令和5年度(2023年)から受験資格が緩和され、会計学科目はだれでも受験可能になりました。税法科目の受験資格も従来の「法律学または経済学に属する科目」から「社会科学に属する科目」に拡充し、より幅広い人が受験できるようになっています。
なお、試験に申し込む際には、受験資格を証明する書類の提出が必要となりますので、事前に準備しておくことが大切です。なお、緩和のみについて詳しくは、以下のページをご覧ください。
会計学科目は受験資格がない
先に触れたように、会計学科目(簿記論・財務諸表論)については、令和5年度・第73回の税理士試験から受験資格の制限がなくなり、どなたでも受験が可能です。
過去には、以下のような条件を満たさなくてはなりませんでした。
- 大学・短大・高専卒業者(法律学または経済学を履修)
- 大学3年次以上で62単位取得者(法律学または経済学を履修)
- 一定の専修学校の専門課程修了者(法律学または経済学を履修)
- 日商簿記1級または全経簿記上級合格者
- 2年以上の一定の会計・法律事務経験者
この緩和により、高校卒業者でも会計学科目を受験できるようになりました。会計学に属する科目のみを受験する場合は、受験資格を証明する書類の提出も不要です。
では、それぞれの受験資格について詳しく見ていきましょう。
税理士試験の税法科目における4つの受験資格
税理士試験の税法科目を受験するには、以下4つの受験資格のいずれかが必要です。
- 学識
- 資格
- 職歴
- 認定
なお、すべての証明書類はコピー可能です。証明書の氏名と現在の氏名が異なる場合は、改姓前後の氏名が確認できる書類(戸籍謄本等)の提出が必要です。また、A4規格でない証明書は、A4用紙にコピーまたは貼付しなければなりません。
参照:税理士試験受験資格の概要|国税庁
参照:受験資格について|国税庁
学識
税理士試験の税法科目において、学識による受験要件は以下のとおりです。平たくいえば、大学や短大を卒業し社会科学の科目を1つでも履修していれば受験資格があります。
| 受験資格 | 証明方法 |
|---|---|
| 大学、短大または高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者 | 成績証明書(卒業年月の記載がないものは卒業証明書も必要) |
| 大学3年次以上の学生で社会科学に属する科目を含め62単位以上を取得した者 | 成績証明書と大学3年次以上であることが確認できる書類(年次の記載がある在籍証明書等) |
| 専修学校の専門課程(修業年限が2年以上かつ課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る)を修了した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者 | 成績証明書(卒業年月の記載がないものは卒業証明書も必要)と課程証明書(都道府県知事等が発行した証明書を専修学校が原本証明したもの) |
| 司法試験に合格した者 | 所管官庁の合格証明書 |
| 旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験または旧司法試験の第二次試験に合格した者 | 所管官庁の合格証明書 |
| 公認会計士試験短答式試験合格者(平成18年度以降の合格者に限る) | 公認会計士・監査審査会会長発行の「公認会計士試験短答式試験合格通知書」または「短答式試験合格証明書」 |
| 公認会計士試験短答式試験全科目免除者 | 公認会計士・監査審査会会長発行の「公認会計士試験免除通知書」または「免除証明書」 |
大学3年次以上で62単位以上取得していれば、卒業前でも受験できます。ただし、社会科学の科目をまったく履修していない場合は、受験資格を満たせません。
学識や資格による受験資格は、成績証明書や卒業証明書、資格試験の合格証明書、登録証明書のコピーを提出しなければなりません。成績証明書や卒業証明書は、卒業した学校で発行されます。遠隔地に住む卒業生向けに郵送で発行してくれる学校も多いです。
個別認定の場合は、国税審議会から受験資格認定申請書を提出して認定を受けなければなりません。認定後に発行される受験資格認定通知書のコピーを提出します。
資格
税理士試験の税法科目における、資格による受験要件は以下のとおりです。
| 受験資格 | 証明方法 |
|---|---|
| 日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者 | 日本商工会議所発行の合格証明書(合格証書は不可) |
| 公益社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限る) | 公益社団法人全国経理教育協会発行の合格証明書(合格証書は不可) |
| 会計士補 | 日本公認会計士協会発行の登録証明書 |
| 会計士補となる資格を有する者 | 公認会計士・監査審査会発行の旧公認会計士試験第二次試験合格証明書または同試験の免除科目が全科目におよぶことを証する書面 |
日商簿記1級や全経簿記上級に合格していれば、大学卒業などの学歴がなくても税法科目の受験資格を得られます。高卒者や大学1・2年生にとっては資格要件の活用が、試験ハードルを下げるための選択肢となります。
職歴
税理士試験の税法科目における職歴では、以下の受験要件があります。
| 受験資格 | 証明方法 |
|---|---|
| 法人または事業を営む個人の会計に関する事務に2年以上従事した者 | 職歴証明書(表題、受験者の住所・氏名・生年月日、具体的な事務内容と期間、会社等の所在地・電話番号・名称・代表者または人事責任者の署名と公印) |
| 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務に2年以上従事した者 | 職歴証明書(同上) |
| 税務官公署における事務またはその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務に2年以上従事した者 | 職歴証明書(同上) |
| 行政機関における会計検査等に関する事務に2年以上従事した者 | 職歴証明書(同上) |
| 弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士の業務に2年以上従事した者 | 登録証明書および当該業務に2年以上従事したことを証する書面(同業者2人以上の証明) |
| 銀行、信託会社、保険会社または日本銀行等特別の法律により設立された金融業務を営む法人における貸付審査事務等に2年以上従事した者 | 職歴証明書(同上) |
基本、会計事務や税理士業務の補助などに2年以上従事していれば、学歴に関係なく受験資格を得られます。高卒者でも会計事務所で働くことで税法科目の受験資格を得ることができます。
職歴による受験資格は指定様式の職務経歴書を作成し、該当する業務に携わっていた会社の署名・捺印をもらう必要があります。受験資格としては離職後でも問題ありませんが、元の勤務先との関係が悪くて頼みづらいといったことがないよう注意しましょう。
認定
税理士試験の税法科目における認定による受験要件は、以下のとおりです。
| 受験資格 | 証明方法 |
|---|---|
| 国税審議会より受験資格に関して個別認定を受けた者 | 国税審議会会長発行の受験資格認定通知書 |
| 外国の大学を社会科学に属する科目を履修した上で卒業した者 | 税理士試験受験資格認定申請書、卒業証明書、成績証明書、和訳文書、大学紹介文書、返信用封筒を国税審議会会長宛に提出 |
| 商工会・青色申告会における複式簿記による記帳(経理)および決算指導事務に2年以上従事した者 | 受験資格認定申請書、職歴証明書を国税審議会会長宛に提出 |
| 信用金庫(組合)・労働金庫・協同組合等における貸付審査事務等に2年以上従事した者 | 受験資格認定申請書、職歴証明書を国税審議会会長宛に提出 |
一般的な受験資格には当てはまらないものの、個別に認定を受けることで受験資格を得られるケースがあります。外国の大学卒業者や特定の業務経験者は、国税審議会に申請することで受験資格を取得しましょう。
税理士試験の受験資格をなるべく早く満たすには?
効率よく、税理士試験の受験資格を満たす方法をご紹介しまには、以下の4つが挙げられます。
- 科目免除制度を利用する
- 会計事務所や税理士法人などで補助業務に従事する
- 日商簿記検定1級または全経簿記検定上級に合格する
- 高専や大学などで社会科学系の科目を履修する
科目免除制度を利用する
税理士試験では、試験分野(税法科目・会計学科目)ごとに科目免除制度が適用されます。いずれか1科目において、基準点を満たした方(一部科目合格者)が対象です。
ただし、自己の修士学位等取得に係る研究について国税審議会の認定を受ける必要があります。無事に認定してもらえれば、以下のような免除が受けられます。
- 税法科目:1科目で基準点合格+研究認定で残り2科目免除
- 会計学科目:1科目で基準点合格+研究認定で残り1科目免除
税理士試験の科目免除制度を利用できれば、すべての科目に合格する必要はありません。受験資格を満たす手間を省き、効率よく税理士試験への合格を目指せます。詳しくは、下記ページもご覧ください。
会計事務所や税理士法人などで補助業務に従事する
職歴による受験資格に、「税理士、弁護士、公認会計士などの業務を補助する事務」があります。会計事務所や税理士法人で、税理士補助といわれる仕事がこれに該当します。この方法であれば、高卒者や大学1・2年生でも税法科目の受験資格を得られます。
補助業務の内容としては、複式簿記による仕訳、決算、財務諸表作成事務などです。事業会社の経理部門などに在職していても、これらに該当しない業務を担当していた場合は、受験資格とは認められません。また、異なる勤務先の職歴でも、通算2年以上の経験があれば問題ありません。
この2年間の実務経験は、税理士登録の条件の「会計に関する事務(貸借対照表勘定及び損益計算書を設けて経理する事務)2年以上」にも当てはまります。2年というと長くかかるように思わるかもしれませんが、試験合格後すぐに税理士登録ができるメリットもあります。
日商簿記検定1級または全経簿記検定上級に合格する
税理士試験における資格による受験資格には、「日商簿記検定1級」、「全経簿記能力検定上級」の2種類があります。高卒者や、大学1・2年生でも税法科目の受験資格を得られる方法です。
合格者は、商業簿記、会計学、工業簿記、原価計算の知識、企業会計に関する法規を理解し、経営管理や経営分析ができるレベルという難易度の高さです。合格に必要な勉強時間の目安は550時間、合格までの受験回数は平均4回程度といわれています。難易度は高いものの、税理士資格の勉強につながるほか、就職・転職の際にはアピールポイントにもなります。
高専や大学などで社会科学系の科目を履修する
大学卒業者が社会科学に属する科目を履修していない場合、放送大学などで社会科学系の科目を履修することで受験資格を得ることができます。
従来の「法律学または経済学に属する科目」から「社会科学に属する科目」に拡充されたため、より幅広い科目が対象となっています。たとえば、放送大学は通信制で1科目から履修できるため、働きながらでも学習可能です。
社会科学に属する科目については、次で詳しく説明します。
税理士試験の受験資格『社会科学に属する科目』とは
税理士試験の受験資格である「社会科学に属する科目」には、以下が含まれます。
- 法律学分野:法学、法律概論、日本国憲法、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法等
- 経済学分野:経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済等
- その他分野:社会学、政治学、行政学、政策学、ビジネス学、コミュニケーション学、教育学、福祉学、心理学、統計学等
また、「専門科目」でなく「教養科目」や「共通科目」として位置づけられている場合でも対象となります。従来は法学部や経済学部の学生・卒業生が有利でしたが、文学部や理工学部の学生・卒業生も受験しやすくなりました。
社会科学に該当するか判断できない場合は?
履修した科目が社会科学に該当するか判断しにくい場合は、学生便覧を確認しましょう。科目名、担当教授、時間数、授業内容等を記載している資料を用意し、文部科学省ホームページの「学科系統分類表」で確認します。
それでも判断が難しい場合は、最寄りの国税局または沖縄国税事務所の人事課税理士試験担当係へ照会することも可能です。事前に確認しておくことで、出願時のトラブルを防止しましょう。
受験資格を満たせても税理士試験の難易度は侮れない
受験資格を満たしていても、税理士試験はその高い難易度と低い合格率から決して侮れません。試験は5科目(会計2科目と税法3科目)で構成され、全体の合格率は低いのが現状です。
たとえば、令和6年度(2024年)では個別科目の合格率は8.0%~18.7%の範囲でしたが、5科目すべての合格率はわずか1.7%となっています。大学院での科目免除といった代替戦略があるのは、この難易度が関係しているためです。より詳しくは、下記ページをご覧ください。
合格に必要な勉強時間の目安
難易度は、税理士試験合格に必要な実際の勉強時間を見ても、予備校が示す目安を上回りやすいです。マイナビ税理士で取り扱った事例では、会計科目で1,300時間(予備校目安の1.5倍)、法人税法では1,800〜2,000時間(足掛け3年)を要していました。
特に事業税では予備校目安の200時間ではまったく足りず、実際には500時間程度となることもあります。税理士試験に挑む際は、予備校の目安を鵜呑みにせず、実際には2倍程度の時間を見込みましょう。より詳しくは、下記ページでも詳しくお伝えしています。
税理士の資格は将来どう役立つ?
税理士の資格は、将来的に以下の役に立ちます。
- キャリアの幅が広がる
- 独立・開業できる
- 年収が上がる
キャリアの幅が広がる
税理士の資格によってキャリアの幅は広がります。税理士の独占業務は、会計事務所や税理士法人以外でも活かせます。たとえば、コンサルタントとして働く場合、税理士の資格があれば税務処理に関する具体的な助言ができます。
税理士資格のないコンサルタントが同じ助言をすると、税理士法違反になる場合があります。また、同じ税理士でも、一般的な税務・会計や経営支援から、国際税務や相続、事業承継などの専門性の高い業務があり、キャリアはさまざまです。
独立・開業できる
税理士にとって、納税義務がある会社その他の法人、個人のすべてがクライアントとなる可能性があります。税理士はクライアントの幅が広く、需要が多いという仕事といってよいでしょう。
一般的な税務申告をメインとする会計事務所や税理士法人から、相続や資産運用に専門特化した事務所など、独立起業するチャンスは多いです。
年収が上がる
税理士の平均年収は700万程度といわれています。この中には会計事務所勤務の税理士1年生から、独立開業しているベテラン税理士まで含まれます。
BIG4などの大手税理士法人勤務の若手税理士400万円程度、マネジャー、パートナーでは1,000万円~1,500万円超も珍しくないといわれています。
また、独立した税理士の場合はリスクもありますが、経営が軌道に乗れば、2,000~3,000万円を超える人もいます。会計事務所や事業会社の経理部門などで働く場合は年齢やキャリアによりますが、一般職より年収は上がるといえます。
税理士試験の受験資格に関するよくある質問(FAQ)
最後に、税理士試験の受験資格について、よく寄せられる質問へ回答します。
税理士試験の受験資格に年齢制限はある?
税理士試験の受験資格には年齢制限はありません。国籍の制限もなく、会計科目(簿記論・財務諸表論)はだれでも受験可能です。税法科目は受験資格の要件を満たせば、年齢に関係なく受験できます。
大学に行かずに高卒でも税理士になれる?
大学に行かなくても税理士になることは可能です。会計科目(簿記論・財務諸表論)はだれでも受験可能で、税法科目は日商簿記1級取得や実務経験で受験資格を得られます。2023年度税理士試験では高校・旧中卒の受験生の合格率は23.8%となっており、学歴より学習の質と量が重要です。
簿記1級があれば税理士になれる?
簿記1級があれば税理士試験の受験資格は得られますが、それだけで税理士になれるわけではありません。税理士になるには税理士試験の5科目合格が必要です。簿記1級は税理士試験の簿記論と範囲が重なる部分も多いですが、試験レベルは異なります。また、税理士試験合格後は2年以上の実務経験も必要となります。
税理士試験の受験資格に国籍の制限はある?
税理士試験の受験資格に国籍の制限はありません。外国籍の方でも受験資格の要件を満たせば受験可能です。外国の大学卒業者は国税審議会の個別認定で受験資格を得られる場合があります。なお、外国語の証明書類は日本語または英語の翻訳文の添付が必要です。ちなみに、税理士登録にも国籍制限はありません。
通信大学や放送大学の単位でも受験資格として認められる?
通信大学や放送大学で取得した単位も受験資格として認められます。社会科学に属する科目を1科目以上履修していることが条件です。ほかの大学と同様に所定の単位を修得すれば受験資格を取得可能です。成績証明書(卒業年次の記載がない場合は卒業証明書も)の提出が必要となります。
職歴証明書は退職後でも発行してもらえる?
退職後でも職歴証明書の発行は可能です。元の勤務先の代表者または人事責任者に依頼しましょう。離職後でも問題ありませんが、元の勤務先との関係が悪いと頼みづらい場合もあります。そのため、在職中に発行してもらっておくと安心です。複数の職場での経験を合算する場合は、それぞれの職場から証明書を取得する必要があります。
受験資格を証明する書類の有効期限はある?
受験資格を証明する書類に明確な有効期限はありません。ただし、発行日から長期間経過した証明書は受け付けられない場合もあります。原則として受験申込年度に発行された証明書が望ましいでしょう。複数年受験する場合は、毎年新たに証明書を取得する必要もあります。詳細は、各国税局の税理士試験担当係に確認するのが確実です。
受験資格について問い合わせる窓口はどこ?
問い合わせは、最寄りの国税局または沖縄国税事務所の人事課税理士試験担当係にできます。個別認定に関する問い合わせは国税庁人事課(国税審議会事務局)が窓口となります。受験申込期間前に余裕を持って確認することをおすすめします。不明点は早めに解消しておくことが大切です。
まとめ
税理士試験の受験資格は、学識・資格・職歴・認定の4つです。令和5年度からは会計学科目の受験資格を撤廃しており、満たすべき条件があるのは税法科目のみとなりました。税法科目の受験資格も「法律学または経済学」から「社会科学」に拡充され、受験しやすくなっています。
受験資格がない場合でも、日商簿記1級の取得や会計事務所での実務経験、放送大学での科目履修など、さまざまな対策方法があります。税理士試験に挑戦する際は、まず自分が受験資格を満たしているかを確認し、必要な証明書類を準備することからはじめましょう。
マイナビ税理士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
マイナビ税理士とは?
マイナビ税理士は税理士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。