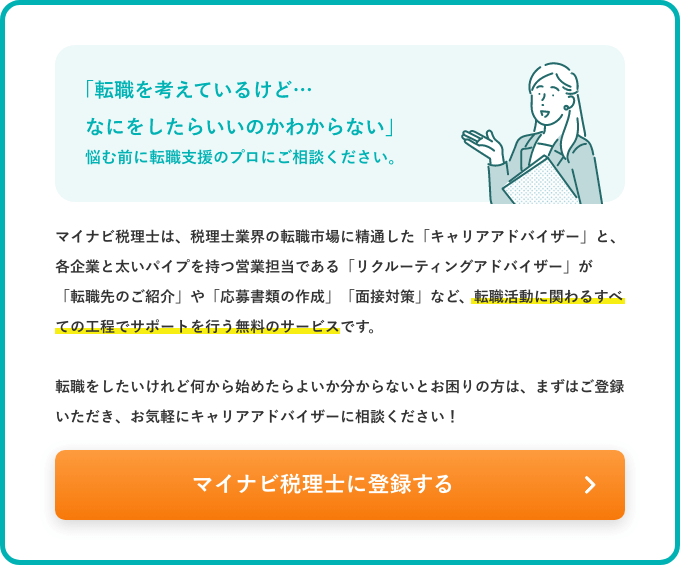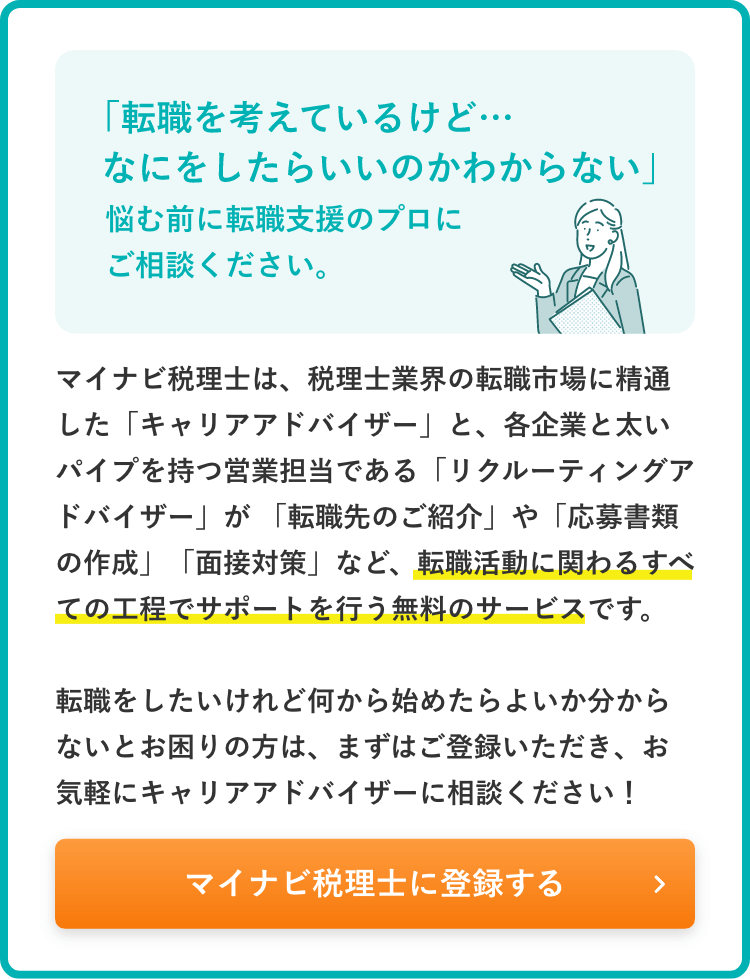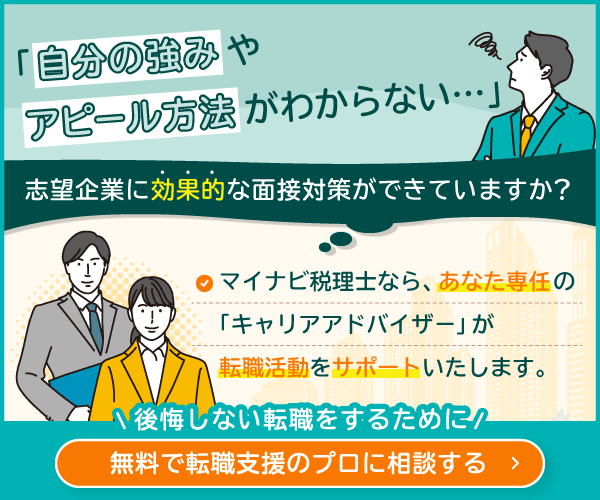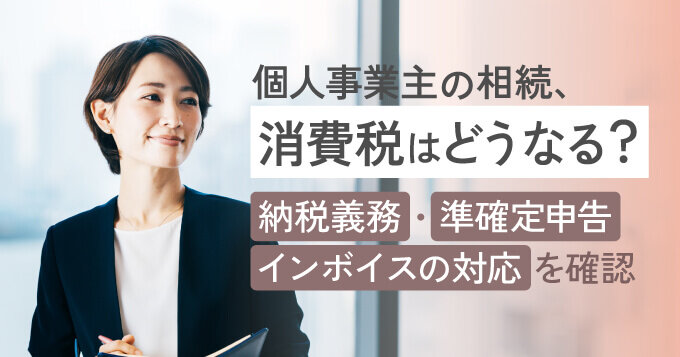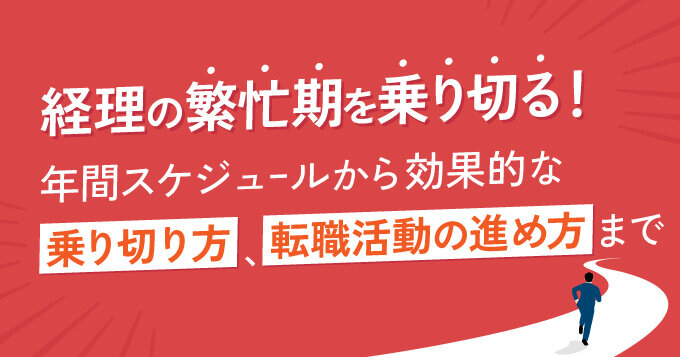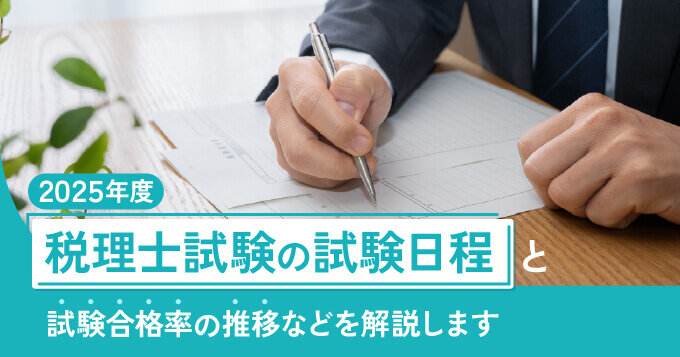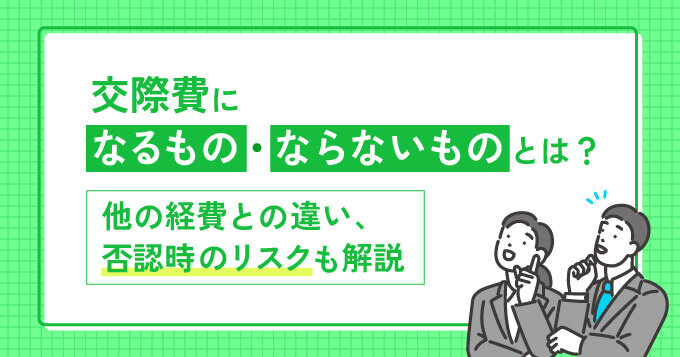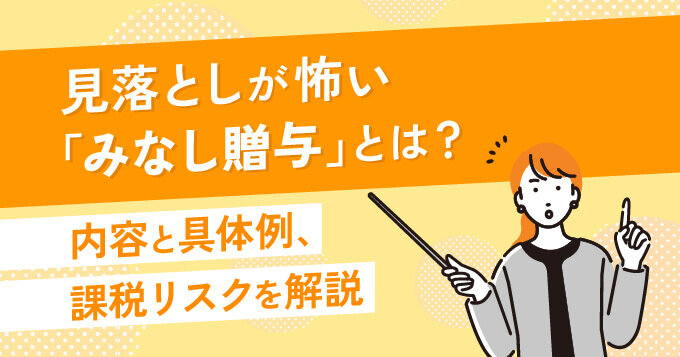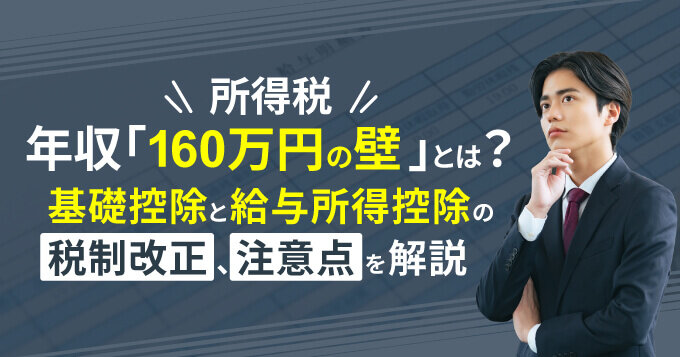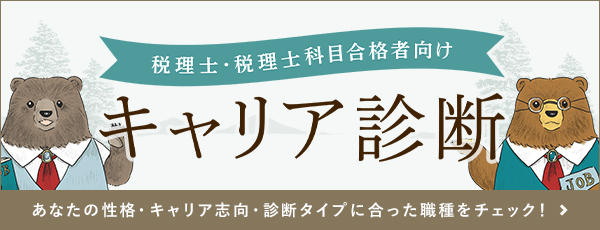【王道は?】税理士試験の科目の組み合わせ方とおすすめ税法科目
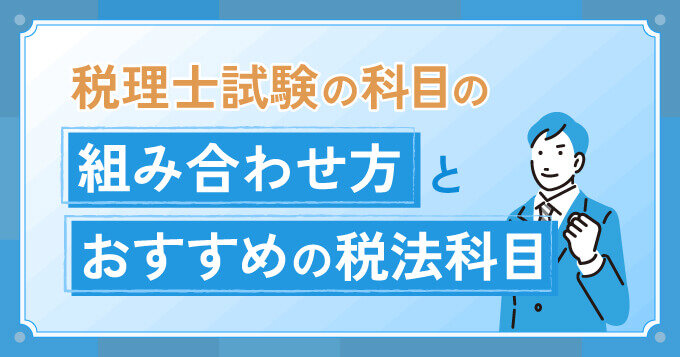
令和4年税理士法改正により、令和5年4月1日以降に実施する税理士試験から、会計学科目(簿記論・財務諸表論)の受験資格要件が完全撤廃され、高校生や大学1・2年生でも受験可能となりました。
また、税法科目の受験の履修科目要件が「法律学または経済学」から「社会科学に属する科目」へと拡大され、文学部や理工学部の学生・卒業生なども受験しやすくなっています。
税理士試験の受験ハードルそのものは下がったとはいえ、会計2科目と税法3科目の合計5科目を選び、それぞれの科目での合格を目指すことになります。その際、安易に「受かりやすそう」という基準だけで科目を選ぶと、後々の実務で苦労したり、キャリアの選択肢が狭まったりしかねません。
そこで本記事では、税理士試験の科目選択におけるルールからおすすめの組み合わせ方まで詳しく解説します。「選び方に悩んで決められない」「おすすめの王道が知りたい」という方は、ぜひ最後までご一読ください。
関連まとめ記事
税理士試験の科目のおすすめは?科目選びのポイントを税理士が解説

監修
マイナビ税理士編集部
マイナビ税理士は、税理士・税理士科目合格者の方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、税理士・税理士科目合格者の転職に役立つ記情報を発信しています。
目次
税理士試験の科目の種類
税理士試験は毎年8月に全国13都市で実施され、3日間にわたって行われます。1年に1度のみ行われる試験で以下の会計学2科目と、税法科目から選んだ3科目の、合計5科目の合格を目指す必要があります。
【会計学科目(必須2科目)】
- 簿記論
- 財務諸表論
【税法科目(3科目選択)】
- 所得税法
- 法人税法
- 相続税法
- 消費税法
- 酒税法
- 国税徴収法
- 住民税
- 事業税
- 固定資産税
実際の合否判定は相対評価で行われ、配点や採点基準は公表されません。ただ、科目合格制を採用しているため、1年に1科目ずつ受験し、働きながら計画的に合格を目指すことも可能です。
5科目を選ぶ際のルール
税理士試験の科目選択では、会計学2科目(簿記論・財務諸表論)を必須とし、以下の条件を満たして税法科目を3つ選択するルールがあります。
- 所得税法または法人税法のいずれか1科目は必ず選択
- 残り2科目は以下から自由選択
- 未選択の所得税法または法人税法
- 相続税法
- 消費税法(または酒税法)
- 国税徴収法
- 住民税(または事業税)
- 固定資産税
このルールに基づくと、税法科目の組み合わせは全部で30通りになります。そのため、実務で活用機会の多い法人税法、消費税法、相続税法などだけに限らず、どのような組み合わせが良いのか悩んでしまうのです。
科目免除とは?
なお、税理士試験では特定の条件を満たす人に対して試験の一部を免除する科目免除の制度も設けられています。主な免除対象者は、以下のとおりです。
- 大学院で修士号または博士号を取得した者(会計学または税法分野)
- 税務署での実務経験が一定期間ある者
- 公認会計士・弁護士資格保持者
特に平成14年4月以降の大学院進学者は、修士論文の研究テーマと1科目合格を組み合わせることで、関連する残りの科目が免除されます。より詳しくは、ぜひ下記ページをご覧ください。
税理士試験の科目ごとの難易度と勉強時間
税理士試験の科目別合格率は、会計科目で20%前後、税法科目で15%前後と推移しており科目ごとに大きな差はありません。また、主な勉強時間は150〜700時間程度ですが、実際には倍の時間がかかると見積もりましょう。
以下で、令和6年度の合格率とおおよその勉強時間をまとめました。
| 科目 | 合格率 (令和6年度) | 必要な勉強時間 |
|---|---|---|
| 簿記論 | 17.4% | 450~500時間 |
| 財務諸表論 | 8.0% | 450~500時間 |
| 所得税法 | 12.6% | 600~700時間 |
| 法人税法 | 16.4% | 600時間 |
| 相続税法 | 18.7% | 450~500時間 |
| 消費税法 | 10.3% | 450~500時間 |
| 酒税法 | 12.1% | 150~200時間 |
| 国税徴収法 | 13.0% | 150時間 |
| 住民税 | 18.2% | 200時間 |
| 事業税 | 13.7% | 200~250時間 |
| 固定資産税 | 18.0% | 250時間 |
特に法人税法と所得税法は、条文量が多く計算問題も複雑なため、十分な学習時間の確保が必要です。一方で、消費税法は比較的条文量が少ないものの、その分、回答に完璧さを求められることから深い理解が問われます。
より詳しく、税理士試験の難易度や合格率について知りたい方は、ぜひ下記ページをご覧ください。
参照:令和6年度(第74回)税理士試験結果表(科目別)|国税庁
受かりやすい科目は『ない』
税理士試験において、「受かりやすい科目」はありません。各科目の合格率に差はなく、むしろ受験者数の多い科目(法人税法、所得税法など)は、優秀な受験者も多く含まれることから、競争が激しくなると考えられるからです。
一方、受験者数の少ない科目(事業税、住民税など)は、一見すると競争が少なく有利に思えますが、参考書や問題集が限られていたり、講座が少なかったりと、学習リソースの確保が課題となります。また、実務での使用頻度が低い科目は、合格後のキャリアにおいても活用機会が限られかねません。
- 自身の得意分野や興味
- 現在の知識レベル
- 将来のキャリアプラン
- 利用可能な学習リソース
- 実務での活用性
科目選択は「易しい科目」を探すのではなく、上記の観点から総合的に判断して選ぶことが大切です。
税理士試験の科目でおすすめの組み合わせ
税理士試験の科目選択でもっとも王道といえる組み合わせは、「簿記論」「財務諸表論」「法人税法」「消費税法」「相続税法」です。実務での汎用性の高さがあり、相互に補完しあって幅広い税務に対応できるからです。
- 法人税法:すべての企業で税務申告に必須で税理士業務の中核となる
- 消費税法:ほぼすべての取引に関係して免税事業者を除く多くの事業者が申告義務を有する
- 相続税法:高齢化社会で相続案件増加が見込まれる成長分野かつ法人経営者の事業承継等でも有効
王道といえる5科目の組み合わせは、税理士として独立した際の業務範囲を広く確保でき、クライアントのニーズに幅広く対応できる強みがあります。また、各科目の学習内容が相互に関連し合うため、学習計画を立てやすいという利点もあります。
税理士は、会計事務所・税理士法人・事業会社で、実務経験を積みながら学ぶ選択肢も可能です。マイナビ税理士では、あなたの希望や理想のキャリアプランに合わせた求人を紹介します。
税理士試験における科目の4つの選び方
税理士試験の科目選択には、王道パターン以外にも目的や将来性によってさまざまな選び方があります。以下では、4つに分けて科目の選び方を紹介します。
- 受験者数の多い順で選ぶ
- 得意な科目から選ぶ
- 実務で使う科目から選ぶ
- キャリアパスから選ぶ
受験者数の多い順で選ぶ
まず、税理士試験で受験者数の多い科目から選ぶ方法です。例えば、令和6年度の場合、受験者数が多いものから選ぶと王道の3種類が挙げられます。
- 消費税法:7,206人
- 法人税法:3,583人
- 相続税法:2,515人
一般的に受験者が多い科目ほど、参考書やオンライン講座、過去問解説などの学習リソースが充実しています。また、年度による合格ラインの変動が比較的小さく、学習の目標設定がしやすくなります。
ただし、受験者数が多いということは、それだけ競争も激しいということです。そのため、逆に受験者数の少ない科目を選ぶことで、競争を避ける戦略を取ることも可能です。
- 住民税:461人
- 酒税法:528人
- 事業税:249人
参照:令和6年度(第74回)税理士試験結果表(科目別)|国税庁
得意な科目から選ぶ
次に、税理士試験の科目から得意分野を選ぶこと方法も1つの選択肢です。効率的な学習計画を立てるうえで役立ち、例えば簿記の資格を持っている方であれば簿記論からはじめるなど、既存の知識をいかしながら学習を進められます。
また、長期戦となる税理士試験で得意分野は学習のモチベーションを維持しやすく、知識の定着も早いという利点があります。得意だからといって油断は命取りになることから、基礎からしっかりと学び直す姿勢は意識しましょう。
実務で使う科目から選ぶ
3つ目の選び方は、税理士試験から実務で使用頻度の高い科目を選ぶことです。将来の実務能力向上に直結する選び方で、働きながら実務で扱った事例と理論を結びつけることで、より深い理解を得られるなどの利点があります。
実務でよく使うものとしては、個人・法人を問わず実務での活用度が高く、多くの税理士事務所で重要視されている消費税法が挙げられます。また、法人税法、所得税法、相続税法も、実務での需要が高い科目です。
これから働きたいと考えている方、税理士補助等の実務から知識の定着を目指したい方にとっては選びやすいでしょう。
キャリアパスから選ぶ
最後に、将来のキャリアパスにもとづいて科目を選ぶ方法です。あくまでも一例ですが、以下では代表的なキャリアパスにおける選択科目の組み合わせを紹介します。
| キャリアパス | 選択科目 |
|---|---|
| 不動産税務スペシャリスト | 法人税法、所得税法、固定資産税 |
| 国際税務コンサルタント | 法人税法、所得税法、消費税法 |
| 事業再生スペシャリスト | 法人税法、国税徴収法、消費税法 |
| 地方創生税務アドバイザー | 法人税法、住民税、固定資産税 |
| 酒類業界スペシャリスト | 法人税法、酒税法、消費税法 |
| スタートアップ税務アドバイザー | 所得税法、法人税法、消費税法 |
※すべてのパターンで会計2科目(簿記論、財務諸表論)は必須です。
そのほか、税務コンサルティングを行っている会計事務所でキャリアを積んでいこうと考えている場合、大企業がクライアントになる場合は法人税の知識が求められるため「法人税」は必須科目です。さらに、企業の会計で必要になる「消費税法」、オーナーの相続対策のための「相続税」などの組み合わせがよいかもしれません。
このように、目指すキャリアパスによって最適な科目の組み合わせは異なります。今後のキャリアパスでどのような知識が必要なのか、ゴールから逆算して科目を決めて「目標」に定めて学ぶと良いでしょう。
税理士試験の科目を受験する順番
税理士試験の科目選択の受験順序では、「簿記論」と「財務諸表論」からはじめるのがおすすめです。簿記論と財務諸表論は同時期に学ぶことで、簿記の仕訳からはじまり、財務諸表にどのように反映されるのか、という一連の流れを体系的に学べて効率が向上します。
また、日商簿記検定といった関連資格をすでに持っている場合、保有する知識を直接活用できるメリットもあります。特に、日商簿記2級以上の保持者は、簿記論の学習時間を短縮できることが多いです。
その後の税法科目については、選択している場合は法人税法からはじめることをおすすめします。簿記・財務諸表の知識が法人税の計算、および申告実務の理解に直結するためです。続いて、消費税法や相続税法など、他の税法科目に進むのが良いでしょう。
あくまでも一例で、実際には自らが学びやすい科目を選ぶだけでも構いません。基礎から応用へと知識を積み上げていくことができ、各科目の関連性をいかしつつ効率を求めて学習を行いたい方はぜひ参考にしてください。
税理士試験は仕事と勉強の両立がおすすめ
税理士試験の勉強と仕事の両立も、だれもが一度は検討しておきたい選択肢です。その理由は、税理士を目指すなら避けて通れない2年以上の実務経験を同時に積めるからです。
実務経験を積みながらの受験には、以下3つのメリットもあります。
- 試験で問われる実務的な論点への理解が深まる
- 税務の現場で活きた知識を得られる
- 合格後すぐに独立開業の準備に入れる
特に会計事務所での勤務は、試験勉強との相乗効果が期待できます。実務で扱う税務申告書や財務諸表が、そのまま生きた教材となるためです。より詳しくは、ぜひ下記ページもご覧ください。
税理士試験の科目の組み合わせに関するよくある質問(FAQ)
最後に、税理士試験の科目の組み合わせに関するよくある質問へ回答します。
税理士試験の科目合格は独学で目指せる?
独学での科目合格は、可能です。ただし、科目ごとの平均合格率は低く、相当な覚悟と計画性が必要です。
- 基礎的な会計知識や実務経験がある
- 1日2時間以上の学習時間を確保できる
- 自己管理能力が高く、計画的に学習を進められる
- 最新の試験情報を積極的に収集できる
上記の条件が整えば、独学でも十分に合格の可能性があるでしょう。特に会計事務所や税理士法人での実務経験がある場合、理論と実践を結びつけやすく、独学での合格確率も高まります。詳しくは、下記ページをご覧ください。
税理士試験の科目は税法から受けるのもあり?
税理士試験では、税法科目から受験をはじめることも可能です。特に税務の実務経験がある方や、税法に関する基礎知識が豊富な方にとっては選びやすく、自らの得意分野や興味からはじめることでモチベーションも維持しやすくなります。
必須科目である簿記論・財務諸表論は避けて通れませんが、最初から取り組む必要はありません。自らの強みを活かせる科目から着手し、決めた科目の勉強をやり抜き確実に合格を重ねていく戦略もまた有効です。
税理士試験は何科目ずつ合格すればいいですか?
科目合格のペースは、自らの生活環境や目標期間に応じて柔軟に設定できるため、1科目ずつでも構いません。1年1科目のペースであれば、全5科目の合格まで5年かかる計算になります。
より短期での合格を目指す場合は、例えば1年目に3科目、2年目に2科目といった計画も可能であることから、無理のない範囲で着実に合格を積み重ねていくことをおすすめします。
まとめ
税理士試験の科目選択は、必須科目である簿記論と財務諸表論、そして法人税法・消費税法・相続税法という王道の組み合わせが、実務での活用度と学習効率の両面で優位性を持ちます。
科目選択の際は、以下4つの視点からの検討が有効です。
- 受験者数の多い科目から選ぶ(豊富な学習リソース)
- 得意分野から選ぶ(モチベーション維持)
- 実務での活用度から選ぶ(即戦力としての価値)
- 将来のキャリアパスから選ぶ(専門性の確立)
科目選択に「正解」はありませんが、自身の状況と目標に合わせた戦略的な選択が合格への近道となります。税理士試験は合格して終わりではなく、合格してからが税理士の道のスタートです。その後のキャリアにとって最適な組み合わせを選びましょう。
マイナビ税理士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
マイナビ税理士とは?
マイナビ税理士は税理士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
あわせて読みたいオススメ記事
カテゴリから記事を探す
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。