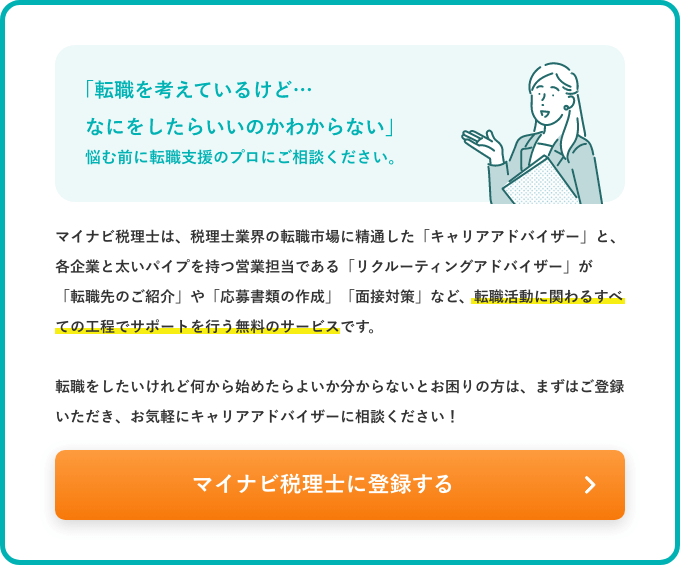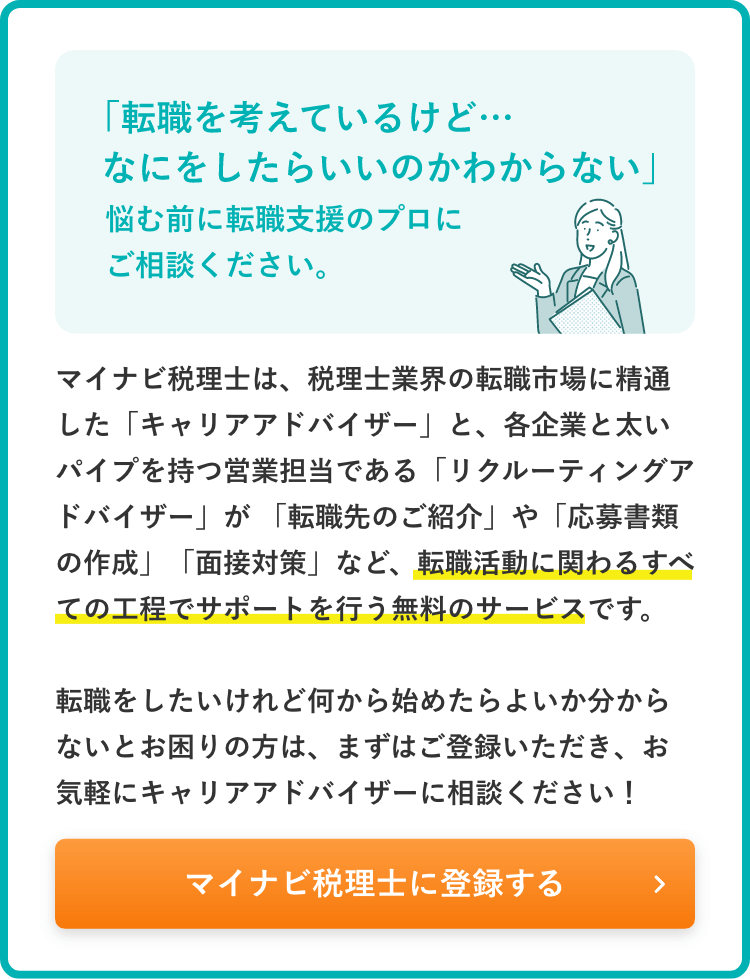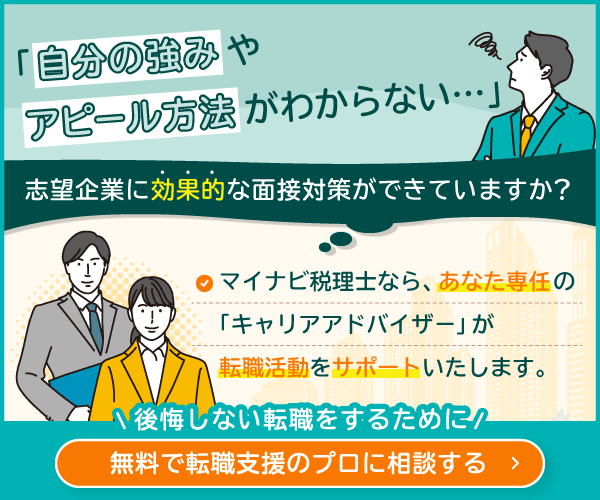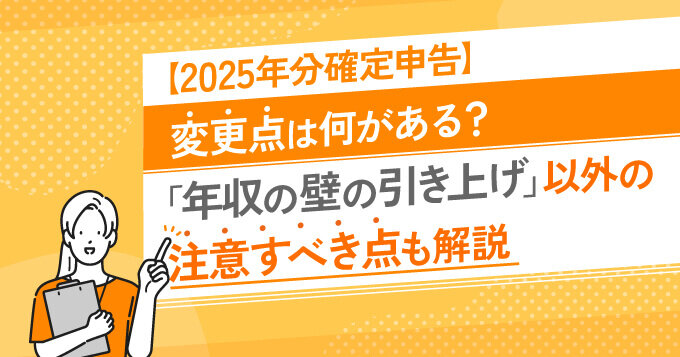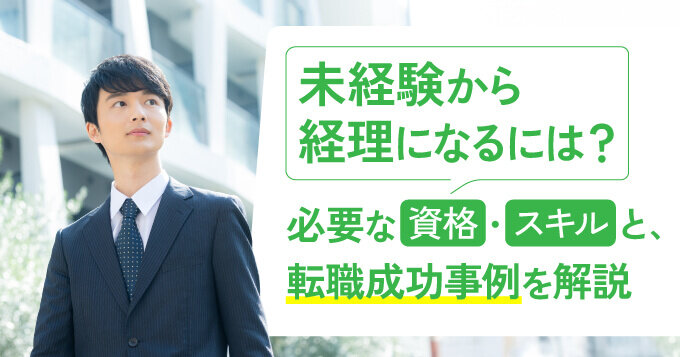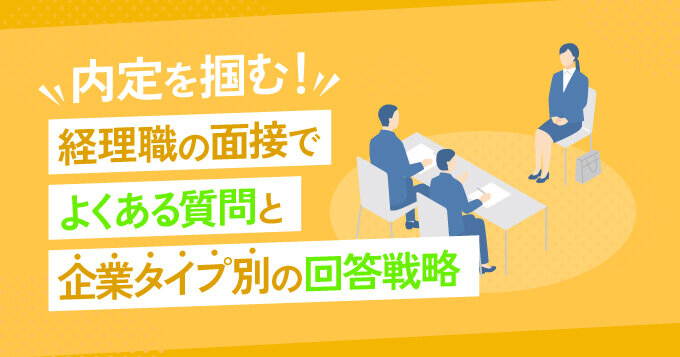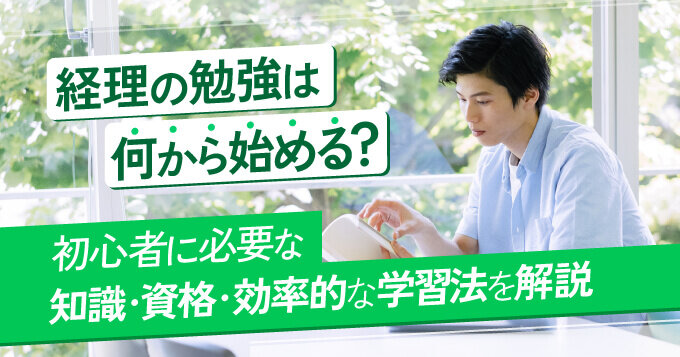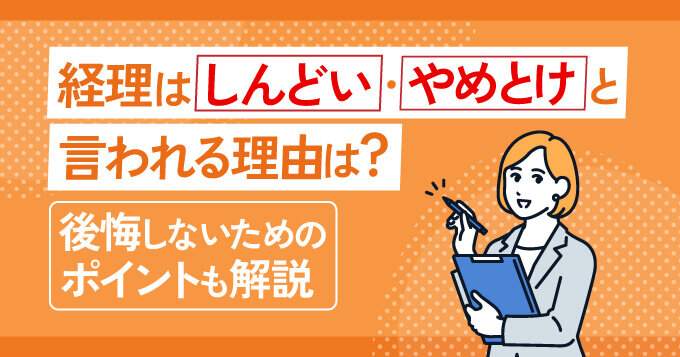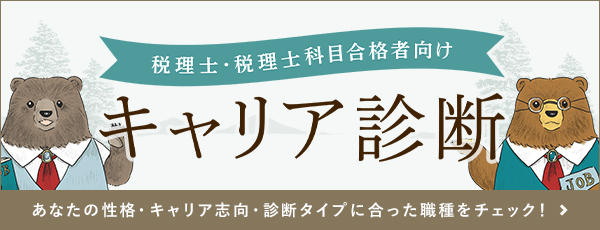税理士をめざせる大学院とは? 通うメリット・デメリットも解説
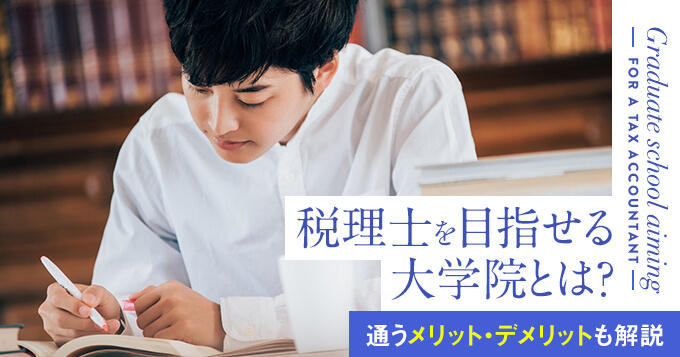
税理士をめざすために大学院で学ぶという選択肢があります。大学院の履修単位や論文の提出実績によって税理士試験の科目が一部免除され、税理士試験が有利になります。大学院に通うためには学費や時間がかかります。税理士をめざすために大学院に通う場合のメリット、デメリットを知り、選択肢のひとつとして検討してみませんか。
税理士を目指す方法には、大学院で学ぶ以外にも、働きながら資格取得を目指すという選択肢もあります。特に働きながら資格取得を目指そうと考えている方は、是非一度マイナビ税理士のキャリアアドバイザーへご相談ください。あなたに適した転職先をご提案いたします。

監修
マイナビ税理士編集部
マイナビ税理士は、税理士・税理士科目合格者の方の転職サポートを行なう転職エージェント。業界専門のキャリアアドバイザーが最適なキャリアプランをご提案いたします。Webサイト・SNSでは、税理士・税理士科目合格者の転職に役立つ記情報を発信しています。
税理士になる3つの方法
税理士試験で5科目に合格する
税理士試験5科目に合格することで、税理士となる資格を得られます。5科目の合格者の氏名などが合格者発表の官報に掲載されるため、官報合格と呼ばれます。科目免除された合格者と区別されるのは、5科目すべてに合格することの難しさを表しています。
実際に、2、3年で合格できればかなり早いといわれ、5年、10年かけて合格する人もいます。税理士としてキャリアを積むにつれて少なくなっていきますが、会計業界には「官報合格者は優秀」と評価する傾向があります。
大学院で税理士試験の一部科目の免除を受ける
税法系もしくは会計系の学位を取得した人は、取得した学位の学問領域に該当する試験科目の一部が免除されます。免除されるのは最大で税法2科目、会計学1科目です。つまり、免除対象となる分野の1科目は試験で合格する必要があります。
税理士法の改正により、2002年(平成14)4月以降に大学院に進学した人は、学位により免除される範囲が変わります。これから、大学院に進学する人もこちらに該当します。修士の学位を取得した場合、該当する学問領域の1科目以上に合格すれば、残りの試験科目の一部が免除されます。博士の学位を取得した場合は、該当する学問領域の科目が免除されます。
2002年(平成14)3月31日以前に大学院に進学した人は、修士と博士のいずれの学位でも該当する学問領域(会計系、税法系)の科目がすべて免除されます。
免除を受けるためには必要な単位を修得したうえで、修士論文が国税審議会の審査で認定されなければなりません。科目免除の手続きは、学位取得証明書、成績証明書、指導教授の証明書、学位を取得した論文のコピーなどの必要書類を揃えて申請します。手続きのタイミングは、科目合格の前後どちらでも問題ありませんが、科目免除を効率よく活用できるよう試験勉強と並行して準備しておくとよいでしょう。
<免除の対象となる科目>
| 会計系 | 必須科目(簿記論、財務諸表論) |
|---|---|
| 税法系 | 選択必須科目(所得税法、法人税法)、選択必修科目(相続税法、消費税法または酒税法、国税徴収法、住民税または事業税、固定資産税) |
税務署に所定の年数以上勤務する
税務署に勤務して国税に従事した人には、経験した職域と勤務年数に応じて科目免除があります。28年以上勤務した場合はすべての科目が免除されます。税務署に勤務していても、国税に従事していない場合は科目免除の対象にはなりません。
| 税法系 | 10年または15年以上、税務署に勤務した国税従事者 |
|---|---|
| 会計系 | 23年または28年以上税務署に勤務し、指定研修を修了した国税従事者 |
<ココまでのまとめ>
・税理士試験5科目に合格するのはかなり難関。
・会計学もしくは税法に関する学位取得で科目免除される制度がある。
・税務署の国税従事者は経験した職域と勤務年数に応じて科目免除がある。
税理士をめざせる大学院の種類
会計大学院
会計大学院は、会計のプロフェッショナルの養成を目的とする専門職大学院です。アカウンティングスクールと呼ばれることもあります。
一般の大学院が研究および研究者の育成を目的とするのに対し、専門職大学院の目的は高度で専門的な職業能力を持った実務家の養成です。会計大学院では研究指導や論文審査はなく、現役会計士を教員に起用した、実践的なカリキュラムを提供しています。
会計大学院の修了には2年間で30単位以上が必要で、会計専門職修士の学位を取得できます。修士論文のテーマが税法関連の場合は税法2科目、会計学関連の場合は会計学1科目が免除されます。科目免除のために会計大学院に進学する人は、税法の研究科を選択するケースが多いようです。さらに3科目が免除されるよう、税法と会計の修士号を取得できる3年間のコースを設けている大学院もあります。
気になる費用ですが、国公立と私立ではかなりの差があります。国立の大学院は入学金、授業料がほぼ同じで、その他の公立大学院は国立に準じるか多少低く設定されていることが多いようです。私学は独自に設定されているため、学校ごとの差異が大きいです。たとえば、私立の入学金は20万~30万円が相場ですが、中には数万円という大学院もあります。
| 入学金 | 授業料(年) | 施設費などその他費用 | |
|---|---|---|---|
| 国立 | 28万2000円 | 53万5800円 | 概ねなし |
| 私立 | 5万~30万円 | 50万~150万円 | 数万円~10万円 |
税理士の科目免除が受けられる大学院
法学、経済学、経営学、商学の大学院の修了者は、税理士試験の科目免除の対象になります。従来の春入学(4月)に加えて、秋入学(9月)の大学院が増え、社会人に対する門戸も開かれています。学部生、社会人を問わず受験できる一般入試と、一定の要件を満たした社会人を対象とする社会人入試があります。
一般的に社会人入試では語学試験と面接のみ、大学院によっては、小論文や研究計画書などの書類審査と面接のみの無試験入学もあります。無試験というと書類提出だけで簡単に入学できるのかと思われがちですが、研究テーマへの理解や知識、研究者としての資質などを厳密に審査されます。
<ココまでのまとめ>
・会計大学院では2年間、30単位以上の履修で会計専門職修士の学位を取得できる。
・修士論文のテーマにより、税法2科目もしくは会計学1科目が免除される。
・法学、経済学、経営学、商学の大学院の修了者は科目免除の対象になる。
税理士科目免除のメリット・デメリット
メリット①早く税理士になれる可能性が高い
科目免除を利用することで、短期間で合格できるメリットがあります。「税理士試験で5科目に合格する」の項で述べたとおり、税理士試験で5科目すべてに合格するのは非常に難しいことです。
一般的に、税理士試験合格までに必要な勉強時間は4000~6000時間といわれています。上限と下限ではかなり開きがありますが、個人差もありますし、主観的な情報も含まれるため、明確な数字を出すことは難しいです。仮に4000時間で合格できるにしても、1日8時間ずつ勉強しても1年半近くかかります。働きながら税理士をめざす場合は、1日平均8時間の勉強時間を確保するのは難しく、3~4年はみなければならないでしょう。
科目免除を利用すれば必要な科目だけに注力できるようになり、かなり負担が軽減されます。
メリット②法律への理解が深まる
税法系の学位を取得すれば、税法に限らず、法律全般への理解が深まります。税理士となって経営コンサルティングを行う際に、民法、労働基準法、下請法など税理士試験の科目にない法律について理解していれば必ずプラスになります。
その知識を活かして行政書士や司法書士の資格を取ってダブルライセンスとなれば、税務と法務を一緒に頼める税理士という強みにもできます。
デメリット①お金がかかる
大学院の入学金と授業料だけで130万円から300万円以上かかります。これは専門学校や通信教育と比較するとかなり高額です。さらに、大学院の課程だけでは税理士試験全体をカバーできないため、試験対策としてダブルスクールで予備校や講習に通う人もいます。
ただし、科目免除だけでなく、学位取得と体系的かつ専門的な知識が身につくことで将来的なメリットは大きく、価値ある投資と考えられます。また、奨学金を受けられる場合があります。
デメリット②大学院に通う時間が必要
学部生ほどは拘束されませんが、大学院に通学する必要があり、そのための時間を割かなければなりません。仕事を持っている人には、夜間制や通信制の大学院もあります。通信制の場合は大学院に出向くのは年に数回程度のスクーリング(面接指導)だけで済みますので、仕事との両立もしやすいでしょう。
<ココまでのまとめ>
・学位免除により、早く税理士になれる可能性が高い。
・200万前後の費用はかかるが、法学もしくは会計学の学位と知識は将来のプラスになる。
・大学院に通う時間がとりづらい場合は、夜間制や通信制を検討してみるとよい。
まとめ
税理士試験合格者の中でも、5科目に合格した官報合格者は高く評価されるといわれています。だからと言って、大学院修了による科目免除を受けることが、就職・転職に不利になることはありません。
大学院の学費や時間はかかりますが、科目免除によって試験勉強の負担が軽減されることは確実です。また、大学院では税法や会計学を体系的に学べるというメリットがあります。税法と会計学は税理士にとっては必須の知識ですから、大学院で学んだことは評価されるでしょう。
マイナビ税理士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
マイナビ税理士とは?
マイナビ税理士は税理士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。