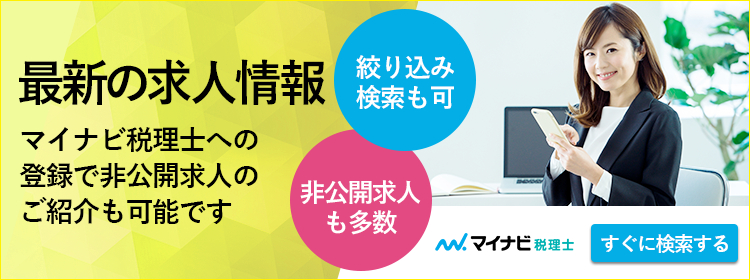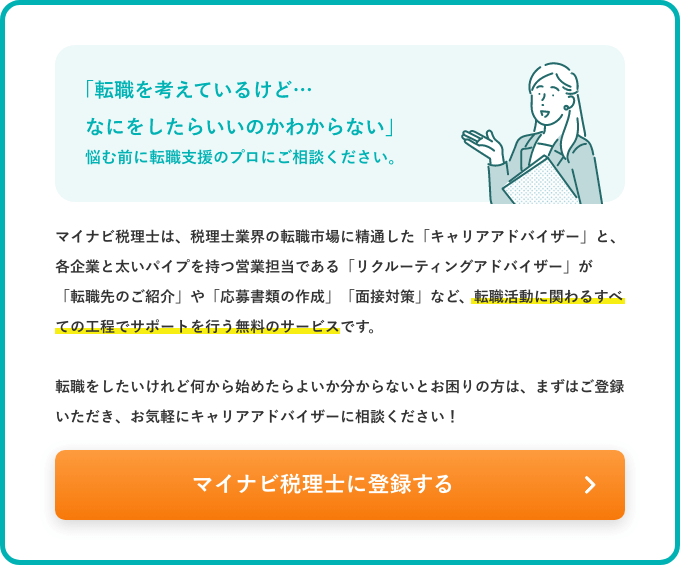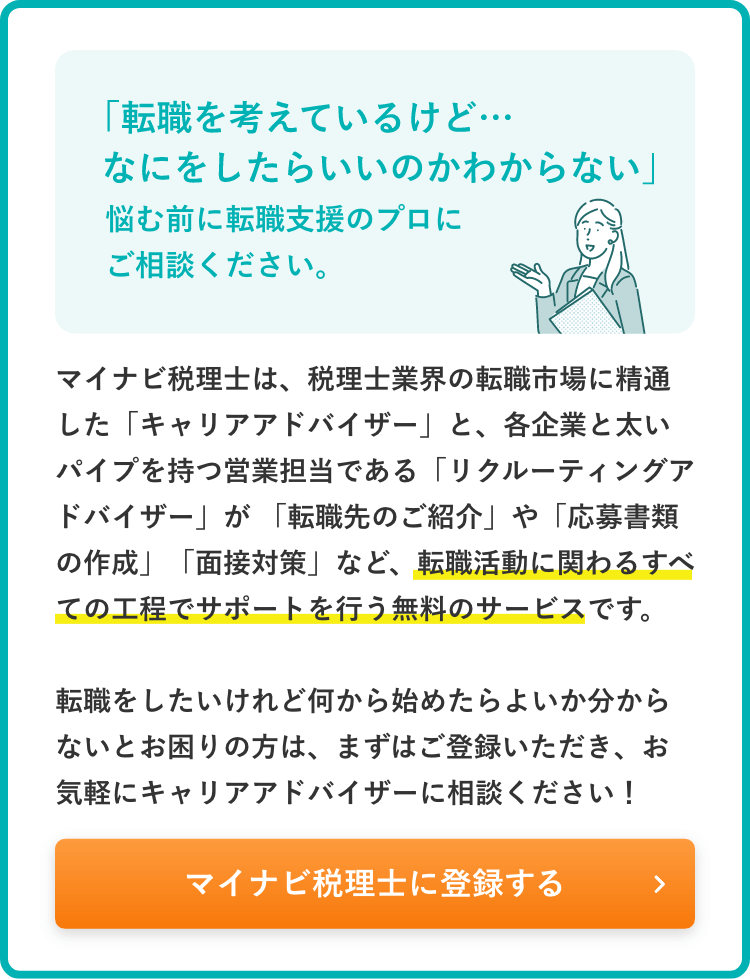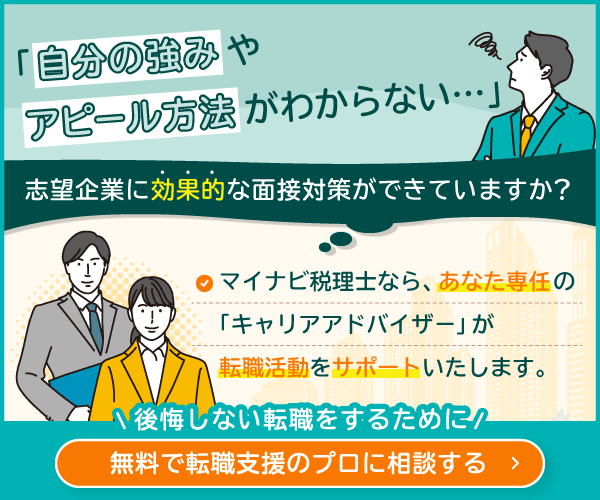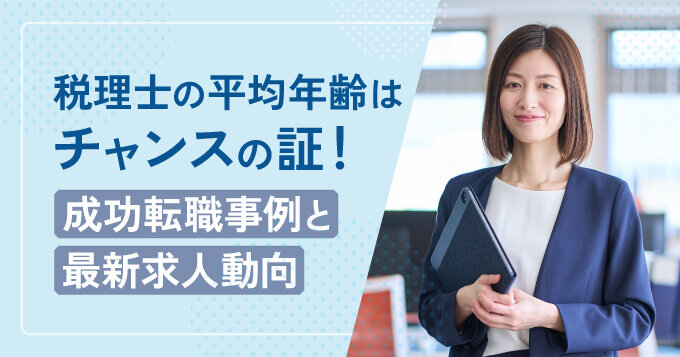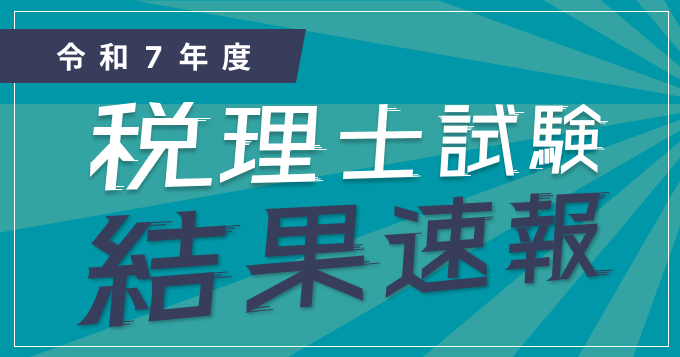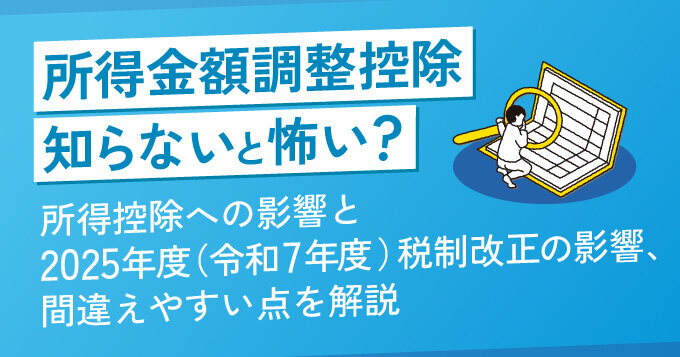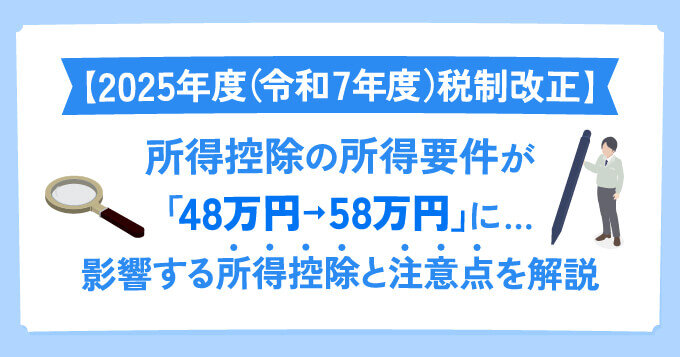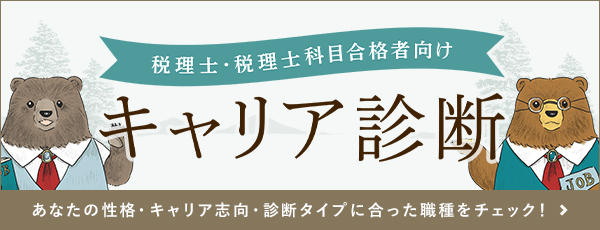法令の「公布」「施行」の意義は?税制改正の流れと対処法を解説
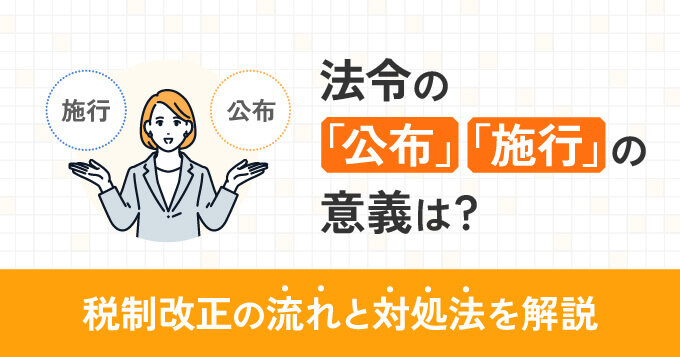
昨今の税制改正においては、「年の途中で改正税法が施行される」という事態が生じました。定額減税そして160万円の壁などです。年の途中での改正法施行は、注意しなければならないことがあります。何に注意しなくてはならないのでしょうか。そもそも「公布」「施行」とはどういう意義を持つのでしょうか。今回は、税制改正の流れとともに、公布・施行の意義、そして年の途中で改正税法が施行された場合の対処法を確認します。
目次
税制改正の流れ
まず「法律(税法)」がどのように成立し、効力を持つのかに至る一般的なプロセスを確認しましょう。
各省庁からの要望
毎年夏頃、各省庁が翌年度の税制改正に関する要望を財務省に提出します。基本的に8月末までです。
税制調査会で審議
秋以降、政府税制調査会や与党の税制調査会(通称「税調」)で、これらの要望や経済情勢を踏まえた改正案の審議が本格化します。
税制改正大綱の公表
例年12月中旬頃に、与党税制調査会が審議の結果をまとめた「与党税制改正大綱」が公表されます。これが翌年度の税制改正の骨子となります。つまり、税の法令の改正はこれを基礎に作成されるのです。
そのため、税理士などの実務家は、大綱が公表されるとすぐに読み込みを開始します。そして実務の現場にどう影響するのかを分析します。
国会審議・可決成立
大綱に基づき、政府が法案を作成します。「〇〇税法等の一部を改正する法律案」というものです。そして翌年1月召集の通常国会に提出し、衆議院・参議院での審議を経て、可決・成立します。成立時期は通常、3月末です。また、ほとんどの場合、提出された大綱ベースの法案がそのまま可決・成立するのですが、まれに国会で与野党から修正案が提出され、大綱にはない新たな法律が成立することがあります。2025年度税制改正の「基礎控除の上乗せ(租税特別措置法)」がこれに当たります。
公布
成立した法律は、天皇による国事行為として公布されます。また、成立した法律・政省令は官報に掲載され、国立印刷局の掲示板に貼られることで、公布された状態となります。
施行
公布された法律は、法律の附則で定められた日(施行日)から効力が発生します。
多くの税法は、3月31日に公布され、翌日の4月1日から施行(適用)されることが一般的です。しかし、昨今は施行日が変則的になるケースが増えています。
公布とは?意義と効果を確認
「公布(こうふ)」とは、成立した法律を、国民が知ることができる状態に置くことを指します。日本では、官報(国の機関紙)に掲載されることによって行われます。
意義
なぜ公布が必要なのでしょうか。これは近代国家の基本原則である「国民主権」と「法の支配」に深く関わっています。
主権者である国民は、自らが選んだ代表者である国会議員が制定した法律によってのみ規律されます。同時に、その法律の内容を知る権利を有しています。国民が知り得ない法律によって処罰されたり、義務を課されたりすることは、憲法の保障する適正な法手続きに反します。税についてならば、国民は法律に基づいてのみ納税の義務を負います。現行税法を変えるなら国会を通じて法律を変えるしかないのです(日本国憲法第30条、第84条)。
つまり、公布は「新しい法律が成立しましたよ」と主権者たる国民に広く知らせる行為です。民主主義の根幹をなす手続きだと言えます。
効果
公布によって、その法律は「存在する」ものとして法的に確定します。ただし、重要なのは、「公布日」=「法律が効力を持つ日(施行日)」ではないことです。
公布はあくまで「お知らせ」の段階です。実際にいつ、その法律によって国民が規律されるのかは「施行」によって決まります。
施行とは?意義と効果を確認
「施行(しこう・せこう)」とは、公布された法律が、現実に効力を発生させることを指します。法律が効力を持つ日のことを「施行日」または「施行期日」と呼びます。
意義
施行日は、国民や企業が新しい法律に対応するための「準備期間」を考慮して設定されます。特に税法のように国民の財産権と義務に直結する法律は、いつから新しいルールが適用されるのかを明確にする必要があります。
効果
施行日が到来すると、その法律は法的な拘束力を持ちます。国民はその規定に従うことになります。もちろん、税理士業界の実務も施行後の法律に従わなくてはなりません。
施行日は、通常、改正法の「附則」の第1条で定められていますが、定めがない場合は法律の公布の日から起算して20日を経過した日から施行されます。なお、税法で施行日の定めがないことは稀です。
年の途中で改正税法が施行されたときの事例
問題は、この「施行日」が一般的な4月1日ではなく、年の途中に設定された場合です。税理士実務に大きな影響を与えた近年の事例を見てみましょう。
定額減税(令和6年度(2024年度)税制改正)
記憶に新しいのが、2024年度税制改正における所得税・個人住民税の「定額減税」です。この改正法は令和6年(2024年)3月31日に公布されましたが、施行日は「令和6年(2024年)6月1日」となりました。
これにより「給与所得者については令和6年(2024年)6月1日以降に支払われる給与等の源泉徴収税額から順次控除(月次減税)する」など、変則的な対応を余儀なくされました。6月という年の途中からのスタートだったため、給与計算ソフトの対応、クライアントへの説明、月次減税額の管理など、税理士事務所は短期間での対応に追われました。
160万円の壁、特定親族特別控除など(令和7年度(2025年度)税制改正)
令和7年度(2025年度)税制改正で議論・決定された、いわゆる「160万円の壁」への引き上げ「特定親族特別控除」の創設などがあります。これらは、令和7年(2025年)12月1日からの施行です。そのため、今年の年末調整や来年3月15日までの確定申告は、あらたな税制をきちんと押さえて対応しなくてはなりません。
年の途中での改正税法施行で起きるリスクと対処法
このように、税制改正が年の途中で施行されると、税理士や顧問先企業にとって様々なリスクが生じます。
リスク
- 情報のキャッチアップ漏れ:「税法改正=4月1日適用」という先入観から、施行日を見落とす。
- システム対応のリスク:給与計算ソフトや会計ソフトのアップデートが間に合わない、または設定ミスが起きるリスクがある。
- 計算ミス:月次処理や年末調整において、改正前後の計算ロジックが混在し、源泉徴収額や納税額を誤る。
- クライアントの混乱:顧問先企業(特に経理担当者)が混乱し、問い合わせが殺到する。
対処法
対処法としては、次のようなものがあげられます。
「施行日」と「適用開始時期」の分離確認
法改正の情報を得る際、必ず「この法律はいつから施行されるか?」と「この規定はいつの所得(取引)から適用されるか?」を分けて確認する癖をつけます。大綱や法案の「附則」を徹底的に読み込むことが重要です。
ベンダーの対応確認
利用している税務・会計・給与システムが、変則的な施行日にいつ対応するのか、スケジュールを早期に確認します。
クライアントへの早期周知
事務所内で影響を分析したら、即座に顧問先へ情報を発信します。「何が変わり、いつから対応が必要で、顧問先(企業側)で何をしてほしいか」を簡潔にまとめます。
還付申告・更正の請求の必要性を確認
定額減税や年収の壁の引き上げのような年の途中の施行は、少なからず還付申告や更正の請求の必要性が高まります。準確定申告などがあった場合に事前にクライアントに知らせておくことが重要です。
まとめ
税制改正は、もはや「年1回、4月1日スタート」という単純なものではなくなっています。定額減税や「160万円の壁」対応のように、年の途中での施行が今後も常態化する可能性があります。
「公布で法律の存在を知り、施行で効力発生の時期を正しく押さえる」ことが重要です。
マイナビ税理士を利用して
転職された方の声
-
 進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士)
進路について適切なアドバイスをしてもらえました!自分の進路について明確な答えが出せていなかったものの、どの業種に進んだら良いかなど適切にアドバイスをしてもらえました。どういったキャリアを積んでいけばより市場価値を高められるのか、候補の会社がどう違うのかを具体的に説明していただけました。(30代/税理士) -
 求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
求人の提案力と面接のフィードバックが良かった!タイムリーな求人の紹介とフィードバックの提供が良かったです。面接前の情報提供では、自分のアピールしたい強みが、面接先企業のどこに符号しており、今後の展開をどう捉えているかの思考の整理をする際に役立ち、安心して面接を迎えることが出来ました。(30代/税理士)
マイナビ税理士とは?
マイナビ税理士は税理士として働く「あなたの可能性」を広げるサポートをいたします。

特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。
特集コンテンツ
- 税理士の転職Q&A
- 税理士の方の疑問や悩み、不安を解消します。
-
【20代】税理士科目合格者
【30代】税理士科目合格者
【20代】税理士
【30代】税理士
税理士業界全般
- 税理士の転職事例
- マイナビ税理士の転職成功者の方々の事例をご紹介します。
-
一般事業会社
会計事務所・税理士法人
コンサルティングファーム
税理士・科目合格者の転職成功事例
税理士・科目合格者が転職で失敗する4つの原因
- 税理士の志望動機・面接対策
- 面接のマナーを押さえ、あなたの強みを引き出す面接対策方法をご紹介
-
会計事務所
税理士法人
コンサルティングファーム
- はじめての転職
- 転職への不安を抱えた方々に向けて転職のサポートを行なっています。
- 税理士の転職時期
- 転職活動の時期や準備時期、スケジュールなどをお伝えします。
- 履歴書、職務経歴書の書き方
- 人事担当者から見て魅力的な職務経歴書を書く方法をご説明します。
カテゴリから記事を探す
税理士業界専門転職エージェント
担当キャリアアドバイザーが
相談~内定後までご支援いたします。